・生き方に悩んでいる方
・「障害」に興味のある方
・インクルーシブに興味のある方
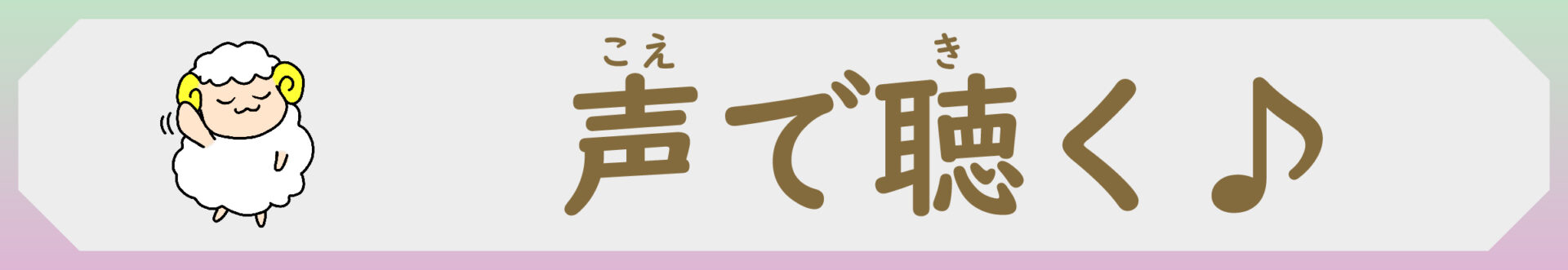
障害とはなにか
障害とはなんだろう。
1980年にWHO(世界保健機関)は、「国際障害分類(ICIDH)」を発表しました。
このモデルは、障害を「機能・形態の障害」「能力の障害」「社会的不利」の三つのレベルに分けて捉え、「障害の階層性」を示した画期的なものでした。
ICIDHでは、障害を「個人の医療ステータス」と考え、「個人の内部にあるもの」と捉えました。
疾病
↓
機能障害(例:耳が聞こえない)
↓
能力障害(例:声で会話ができない)
↓
社会的不利(例:必要な情報が得られない)
2001年、WHOはICIDHを改定します。
新しく発表された「国際生活機能分類(ICF)」では、障害を「活動や参加の制限」と捉え、制限の要因として従来の「個人要因」に加えて「環境要因」が設定されました。
障害が「環境と個人の相互作用の問題」であると考える、現代の「障害観」がここから始まります。
もっと簡単に説明すると「障害は『個人と社会の間にある【生きづらさ】である』」ということです。
個人要因(例:目が見えない)
↓
活動・参加の制限(=障害)
↑
環境要因(例:点字がない、周りの人が助けない)
ICFの発表から20年以上経った今、障害者・健常者問わず、日本の社会で障害をこの定義で捉えている人はどれくらいいるでしょうか。
「障害の診断」の意味
目に見える障害から目に見えない障害まで、日本では基本医師によって障害の診断が下されます。
では、障害の診断は受けなければならないのか?
これもよく聞かれます。
まずは、診断の意味を考えてみたいと思います。
あくまで「支援者から見た診断の意味」です。
ご了承ください。
医学的に自分を知る
診断を受けるということは、自分を知るということです。
医学的に見て、
自分は何が得意で何が苦手なのか。
どういったことができなくて、どういった助けが求められるのか。
人が生きていく上で「誰かに助けを求める力」は必須です。
そのためには自分を知らなければならず、「診断」は医学的に自分を知る手助けをしてくれます。
また、「診断」は時に「名刺代わり」になることもあります。
「それだけではその人となりは分からないけれども、どういう人なのか想像できる」アイテムでもあります。
助けを求めるためのパスポート
公的機関・サービスの中には、障害診断があって初めて利用できるものがあります。
児童発達支援・放課後等デイサービス、精神・身体手帳での控除など…。
そこから考えられることは、障害診断は「助けを求めるためのパスポート」でもあるということです。
「私は困っています・特定の状況で困ります」というサインでもあります。
自尊心を守る
文字が書けない人がいたとします。
その人は「なんで他の人と違うんだろう」「自分は劣っている、努力不足」と思うかもしれません。
医学的に「あなたは元々文字を書くのが難しい人なのかもね」と診断されてそれを伝えられれば、「努力不足」の呪縛から解放されることもあるでしょう。
しかし、逆に劣等感を抱くこともあります。今まで努力してきたことに「できません」と言われるようなものですから。
必要なサポートに理由をつけられる
黒板の板書を写せない人が、カメラで板書を撮ります。
本人は「一人だけ特別扱いで嫌だ」と思うかもしれませんし、周りの人は「なんであの人だけ?」と疑問に思うかもしれません。
医学的に説明されることで、そのサポートが自分に必要であると認識でき、他の人にも説明できます。
「特別扱い」への思いはまた別であることも多いですが、今後のサポートも受けやすくなるかもしれません。
現代日本において、「医学」はとても大きな責任と力を持ちます。
障害児・者支援でも必須であるのは、公的機関・サービスが「医学的証明」を必須としていることが多いからです。
それにより偏見が生まれることもありますが…。
障害診断を受けなくてはいけないのか?の問いへの答えは、
「診断を受けるかどうかは基本的に自由」です。
上述のメリットを得たければ、受ければよいのです。
もちろんまだまだ障害に対しての偏見が強い社会ではあるので、診断を受けるデメリットもあるとは思いますが、基本的にメリットの方が大きいです。
障害者を名乗ること
私は、「障害者と名乗るかどうか(障害があると伝えるかどうか)」も自由だと思っています。
ポイントは「助けが必要かどうか」です。
伝えるメリットとしては、自分は助けてもらいやすくなり、相手は助けやすくなります。
デメリットとしては、偏見により人間性・できることできないことを決めつけられたり、待遇が変わったりするかもしれません。
まとめとしては、「自分に障害があるかどうかは自分で決めればいい」。
そもそも障害は、自分と社会との間にある「生きづらさ」ですから、当然です。
これは決して優しいばかりの考え方ではありません。
「生きづらさ」は自分で発信しなければなりませんし、「障害があるから仕方ない」ではなく「適切な助けを求める力」が必要とされます。
ですが、私はICFの障害観が好きです。
人間として対等であるからには、対等な「生き抜く力」が求められますし、「生きづらさ」を一緒に考える社会が不可欠だと感じます。
「障害者」「障害」のラベルは、自分で貼るものです。
障害告知について
特に見えない障害について、保護者さんからお悩みの相談を受けます。
「障害告知をどうしたらいいでしょうか」
まず、障害告知をする・メリットは、前述の「障害診断を受けるメリット」とほぼ同じです。
保護者にとっては、本人と得意・苦手なことや生き方のお話がしやすくなる、というメリットがあります。
ではなぜ、障害告知をするのでしょうか。
知ってても知らなくても、その子はその子。
障害告知をしないメリットは、
「『障害があるから仕方ない』という投げやり姿勢を防ぐ」
「本人が自分に障害者・障害のラベルを必要に応じて貼れるようにする」
生きていくために「するメリット」「しないメリット」もすべて必要であり、それらは周りの大人がすべてサポートすることができます。
障害告知は「手段」であり「目的」ではありません。
「障害告知を通してメリットを得てもらう」
「周りがサポートできない部分を障害告知によってカバーする」
こういった視点が、個人的には大事だと感じます。
ぜひ障害告知は周りの支援者と一緒に、必要かどうかから考えてほしいと思います。
障害のない社会へ
障害は「個人と社会の間にある『生きづらさ』である」と、お伝えしました。
「生きづらさ」がなければ「障害」もなくなるわけです。
社会を作るのが一人一人違う人間である以上、完全には不可能ですが、私が考えるヒントを最後に1つ置いておきます。
それは
「甘え、甘えられる社会」
です。
少なくとも日本の教育では、「上手な甘え方」は教えてもらえません。
ともすれば「大人は甘えない」なんて言われたりもします。
しかし、甘えない人間などいません。
また別記事に書く予定なので、ここではさらっと例で終わりたいと思います。
お仕事でストレスのかかることがありました。
お家に帰ってきて、家族に言います。
私は家族のために頑張って働いてきたんだ!と怒る。
今日はお仕事で嫌なことあった!聞いて!そして労わってくれ!!と宣言する。
どちらも、家族に対する「甘え」です。
前者は、あまり人を助けられません。理由は、自分が助けを求められていないからです。
後者は、人を助けられます。理由は、上手な助けの求め方(甘え方)を知っているからです。
上手な甘え方(助けを求め方)を知っている人は、他の人に上手な甘え方を伝え、他の人の甘えをキャッチできます。
みんな、今日から身近な人に「こうやって甘えてほしい」と伝え、相手の甘えを受け取ったら自分も甘えてみましょう。
それでは、またお逢いしましょう。
ばいちゃ。
【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】
発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。
通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。
「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」
三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。
現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。
是非お困りごとをお聞かせください。
※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。


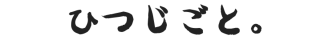
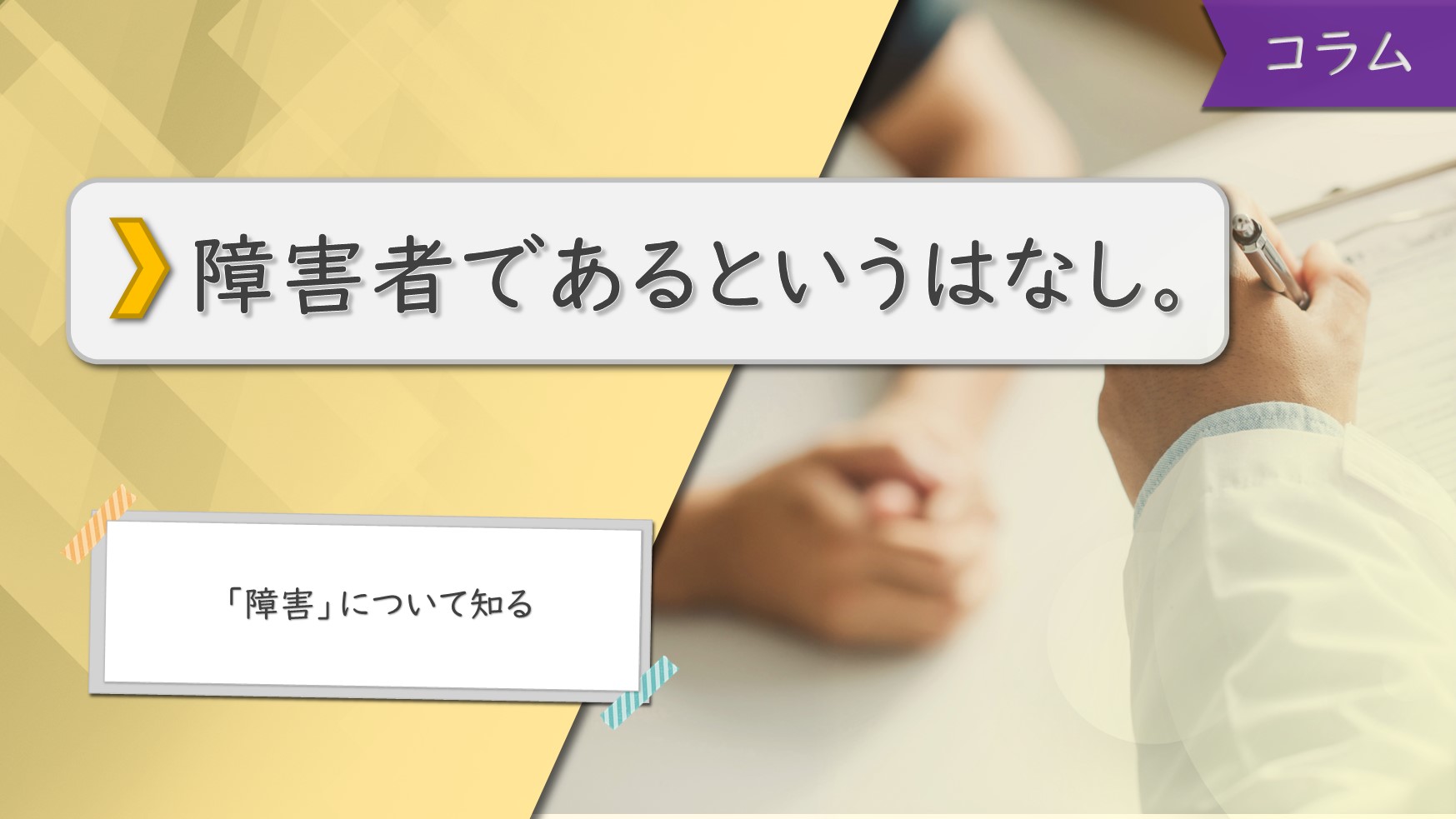
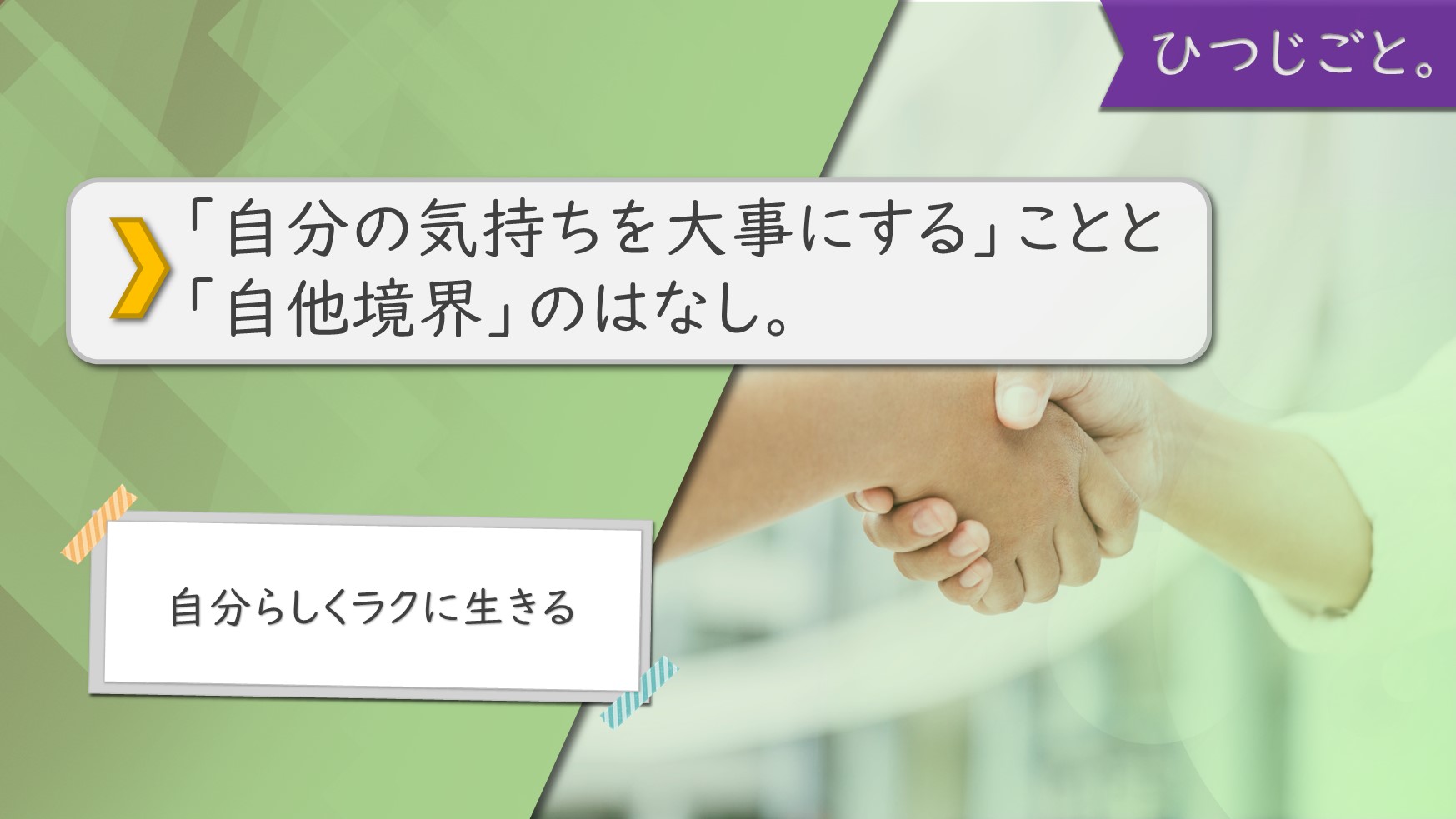

コメント