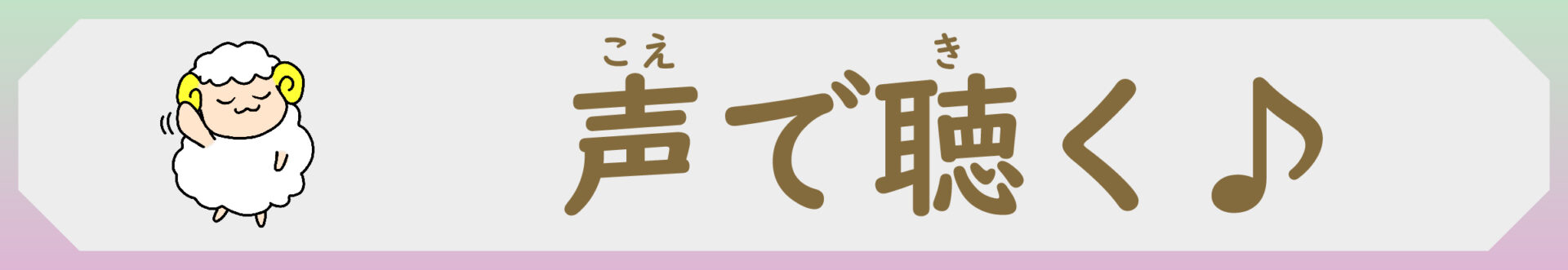
みかんは空気。どうも、ひつじぃです。
はじめに
自閉スペクトラム症(ASD)は、発達障害の一つとして今や社会的に広く知られる言葉になりました。
しかし一方で、誤った知識や偏見が多く見られるのも実情です。
このシリーズでは、自閉スペクトラム症について、できる限り正確に、色々な方向から見ていきたいと思います。
言葉や概念が社会に認知される流れとして、多くの誤解や偏見が生まれてしまうのは必然だと思います。
言葉や概念が広く認知されるのはとても嬉しいことです。
だからこそ、正しい知識を知ってもらいたい、という思いでこの記事を書きます。
お付き合いいただけますと幸いです。
以後、自閉スペクトラム症を「ASD」と呼びます。

「正確に正しく伝える」ことを重視するので、ちょっと堅苦しいけど、ちらっと見ていってね!
ASDの主な特徴
ASDは、人との関わりやコミュニケーションなどの社会性の困難、想像力の困難、過度のこだわりなどをその特徴とします。
ASDの主な特徴
・人との関わりやコミュニケーションの困難
・想像力、見通しの困難
・こだわりや反復的な行動
・感覚の過敏さ、鈍感さ
詳細はこちらにて。
法的側面から見るASD
まずは、日本の法律でASDどのように定義されているか、「発達障害」というくくりも含めてみていきます。
●発達障害者支援法
2004年制定、2005年施行。
発達障害者に対する「支援の在り方」に関して示した法です。
この法律では、発達障害を以下のように定義します。
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」
●文部科学省定義
2003年「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」より
「自閉症とは、3歳くらいまでに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。」
本文:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361204.htm
少し古い法律になりますが、これらが日本におけるASDの定義です。医学的な面が強調され、「脳機能障害」としての側面が強く表れています。

正直、かなりネガティブな記載が目立ちます。「困っている人のための法律」なので「困り感」が前面に出る書き方ではあるのですが、個人的にはASDに関して「機能不全」とはあまり書いてほしくないな…と感じてしまいます。
診断から見るASD
次は、世界的な発達障害診断から、ASDを見ていきましょう。
●DSM-5
2013年、アメリカ精神医学会により公開。
精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版。
世界で最も使用されることの多い医学的診断基準。
これまで自閉症の中の分類として定義されてきた「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」といったサブグループを廃止。
スペクトラム(連続体)として捉え直し、自閉スペクトラム症として定義。
DSM-5では、「スペクトラム」という概念が導入され、「ASDかどうかの境界は曖昧である」と人間的な要素が加わりました。
これにより、グレーゾーン支援がとても積極的に行いやすくなった・障害名ではなく困りごととして認識しやすくなったと感じる一方、
社会的に「自閉スペクトラム症・ASD」というものが何なのかを捉えにくくなった、と感じます。
これは「自閉症」「ASD」といった言葉が独り歩きしているために起こることであり、それによって発生する「困りごと」に焦点を当てられていない社会の在り方が見えてきます。
このあたりの話は私の感想も入ってくるので、先々の記事でまとめたいと思います。
DSMの他に、国際的な診断基準としてICD(国際疾病分類)というものがあり、WHOによって作成されています。2018年6月に最新版のICD-11が承認されました(施行は順次行われる)。
日本の行政機関ではICDが使われていますが、その中の精神障害・発達障害に関する項目にDSMが対応しているため、それほど大きな違いはありません。
ここからは診断基準です。かなり小難しいことが書かれているため、飛ばしてしまっても良いかと思います。
ASDが医学的にどのように診断されるのか知りたい方はお読みください。
●DSM-5の診断基準
A:複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥
(1) 相互の対人的・情緒的関係の欠落
(2) 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥
(3) 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥
B:行動、興味、または活動の限定された反復的な様式
(1) 常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話
(2) 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式
(3) 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味
(4) 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味
C:症状は発達早期に存在していなければならない
D:その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている
E:これらの障害は、知的能力障害または全般的発達遅延ではうまく説明されない
ここでも同じく「困りごと」に焦点を当てる方向性が見えてきます。
今の日本の社会における「発達障害」の捉え方の一歩先を行っていますね。
脳科学から見るASD
脳機能の局在論
難しい言葉ですが、簡単に説明すると「脳は場所ごとに独立していて、それぞれの仕事を担当している」ということです。
例としては、視た情報を処理する「視覚野」と、言語を処理する「言語野」は、脳の別々の場所にありますよ、ということです。
ここから考えられことは、「発達障害の特性は、脳の一部がうまく機能していない or 機能しすぎてしまっているのではないか」という仮説です。
ある交通事故に遭った人が、「虫が横や縦に動いているのは分かるのに、斜めに動くと分からなくなる」と言いました。ここから考えられることは、「縦・横・斜めの動きを把握する」脳の場所は、それぞれ別なのかもしれない、ということです。
こう考えると、一つ一つの行動をさらに細分化して見ることができます。
「あの人は斜めに動いた時だけ動きの把握が難しいのかもしれない」なんて。
とても面白いですね。
社会脳(側頭葉、前頭前野、偏桃体など)の障害
脳には様々な機能がありますが、人が社会を形作るのに必要な社会的行動を司る部位を「社会脳」と呼びます。
具体的には、
・前頭前野…他者の考えや感情の推測、社会的な文脈を考えて適切な意思決定をするなどの機能
・側頭葉…他者の表情の読み取り、他者の視線の読み取りなどの機能
・偏桃体…自分の感情を認識する機能
などがあります。
ASDの人は社会行動の困難が大きいため、社会脳の何らかの機能不全、もしくは異なる発達をしているのではないかと考えられています。

脳科学的には「ASDの人は定型発達者とは違う発達をしている」と、「障害」としてより「新しい人間の形」として捉えている側面を感じられます。
おわりに
さて今回は、法的側面、診断的側面、脳科学的側面に関して見ていきました。
ひつじぃが一番好きなのが、脳科学的な考え方と、次回ご紹介する心理学的な考え方です。
何が好きかというと「ASDの特性を持った人は、定型発達者とは違う可能性を秘めている・違う発達の仕方をしている」というポジティブな面が見られるからです。
私は、ASDの人たちを「自分たちとは違う能力を持った人たち」と捉えたい。
欠落している人、なんて、自分たち本位で彼らを見たくないのです。
ということで、次回は心理学的側面に関してお話をします。
一緒に不思議の世界を見ていきましょう。

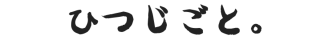
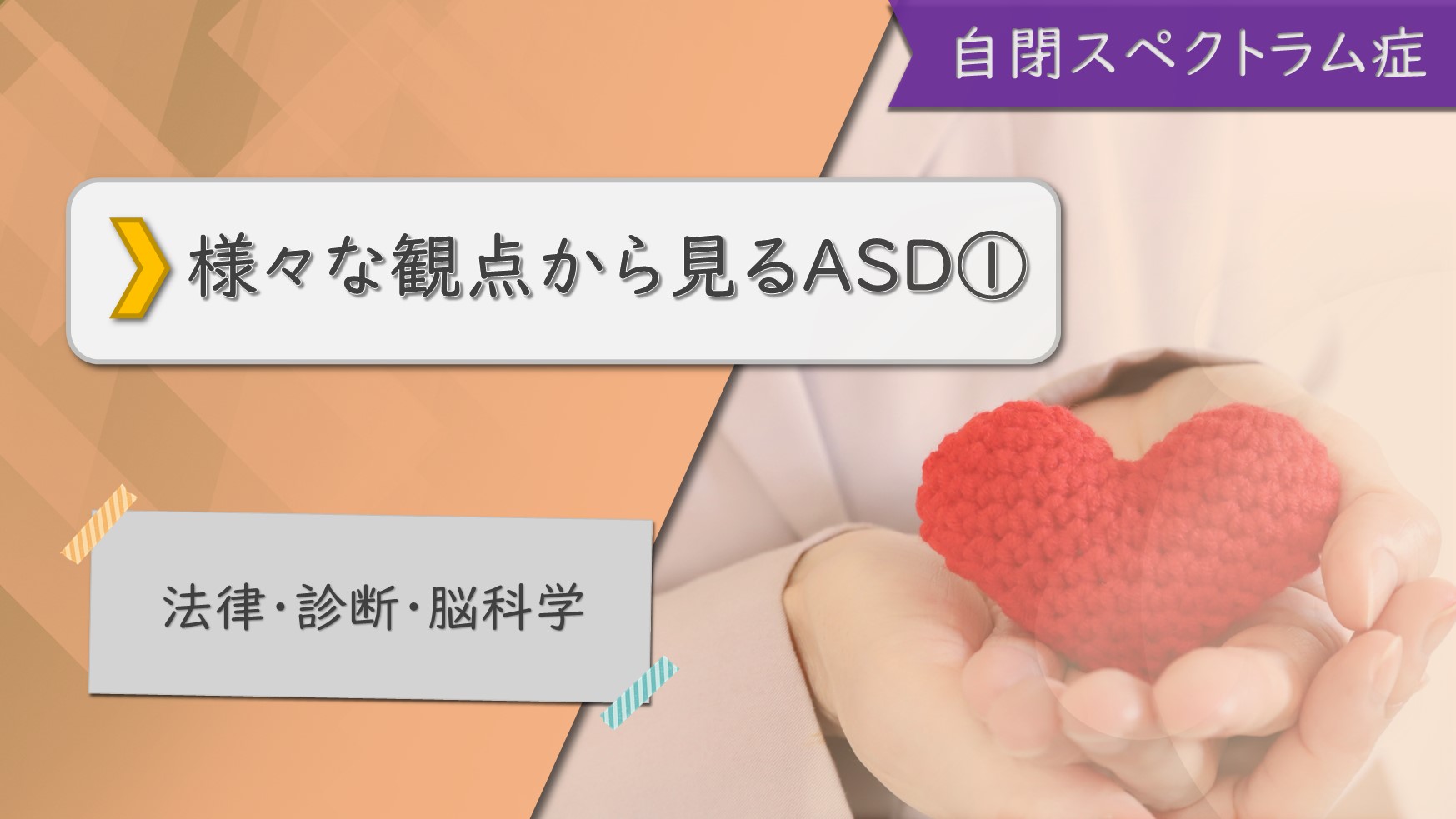
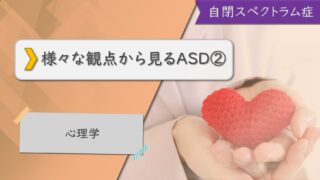
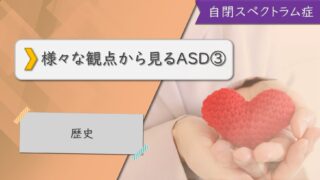
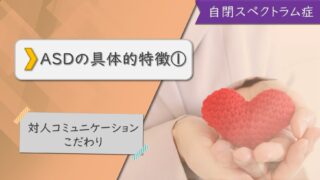
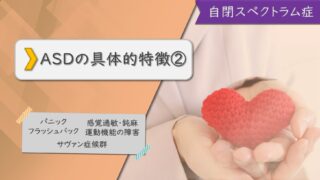
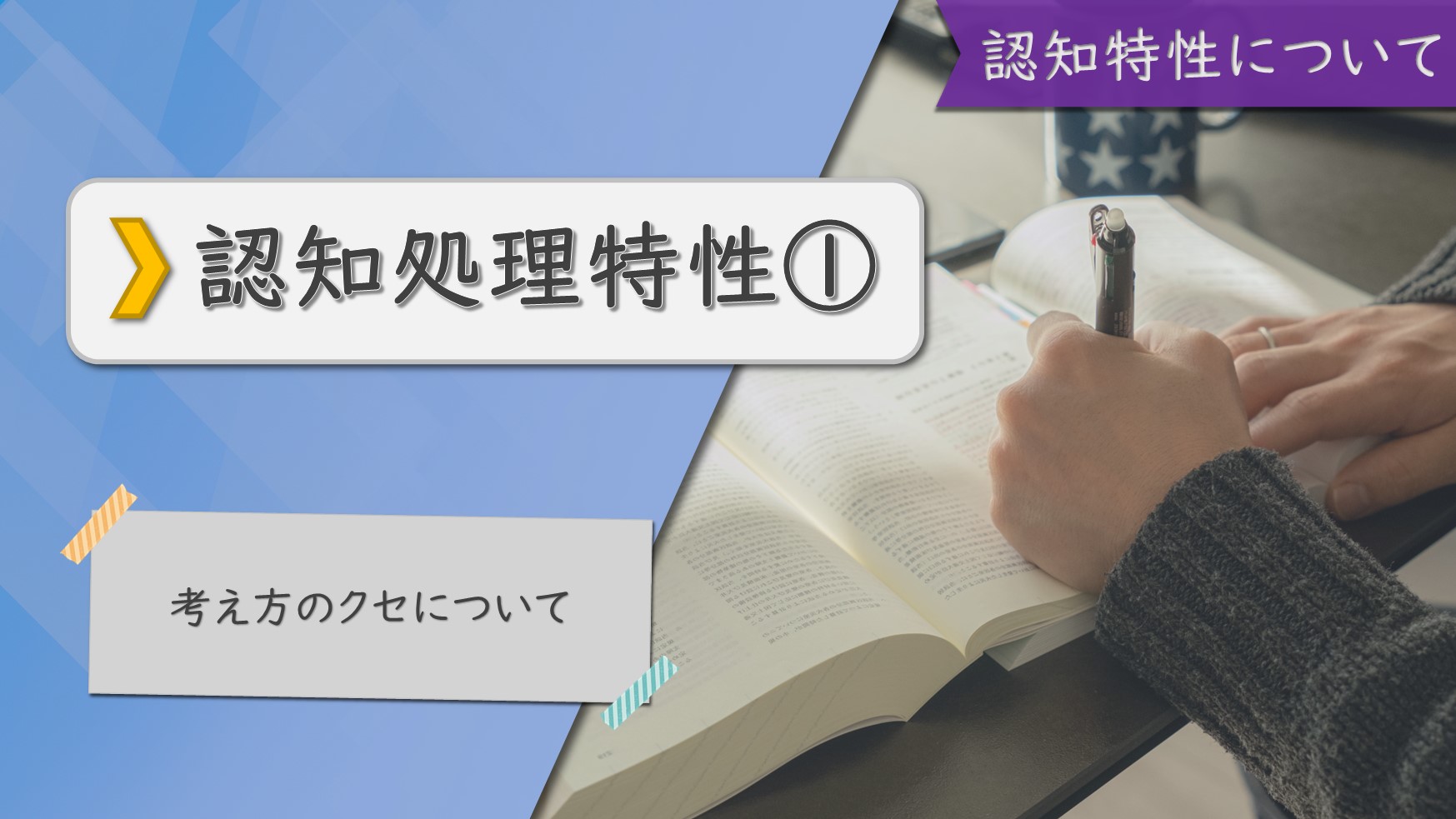
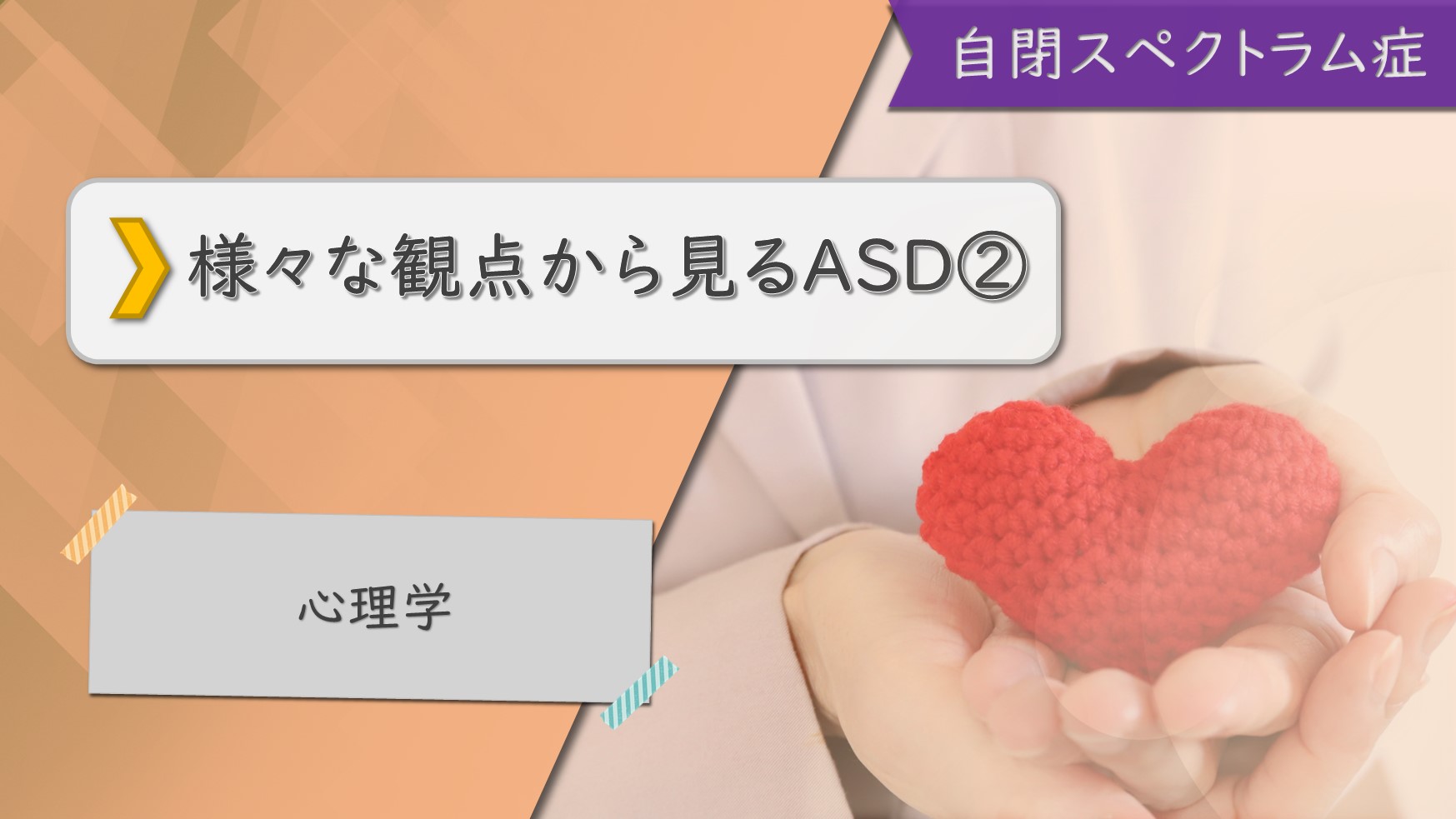

コメント