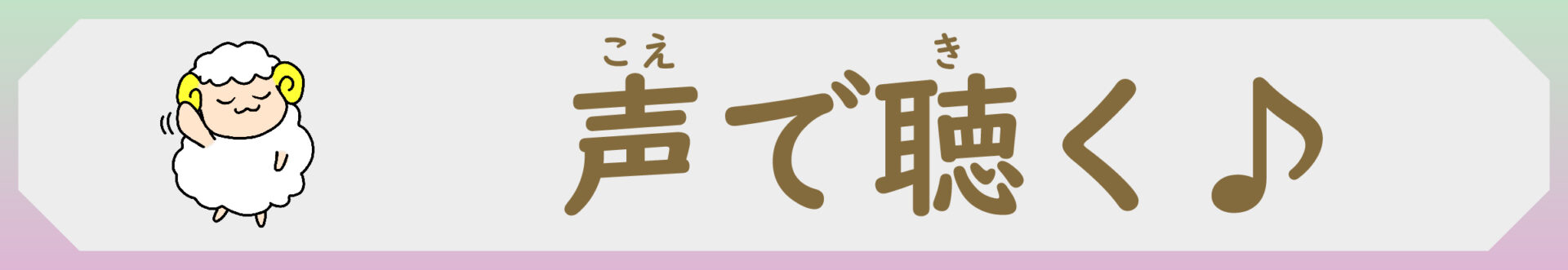
子どもたちと仲良くなるコツは、アホになることです。
心の中に三歳児を迎えましょう。
小学生に「バカじゃないの」と言われたら初心者卒業です。おめでとうございます!(大真面目)
どうも、ひつじぃです。
はじめに
この記事では、自閉スペクトラム症(ASD)を、歴史的視点から見ていきます。
自閉スペクトラム症がどのような歴史を辿って今に至るのか。その歴史を軽く紐解きます。
今回は歴史ということで、残念ながら現在のお困りごとに役立つものはありません。
しかし、歴史を知るということは、同じ間違いを繰り返さないこと、未だ社会に残る偏見を知ること、それらに対しどうアプローチをかけていったらよいのかを知ることに繋がります。
しかし単調であることには変わりないので、興味のある方のみ、お楽しみください。
その他の方は次の記事へ飛んじゃいましょう。
以後、自閉スペクトラム症を「ASD」、非ASD者を「定型発達者」と呼びます。

実はひつじぃ、歴史学専攻です!
発見(1943年)
自閉症の発見は、意外と最近の第二次世界大戦期、1943年。アメリカの児童精神科医であるレオ・カナーにより初めて報告されました。「常同行動・高い記憶力・機械操作の愛好」などを特徴とする11名の子どもたちをもって「早期幼児自閉症」と名付けました。
自閉という言葉は、統合失調症で用いられていた「自閉(Autism)」という言葉を借りたものです。カナーは自閉症を早期に発症する統合失調症に似た症状、つまり後天的な精神疾患の一つと考えていました。
また、1944年、ハンス・アスペルガーは、カナーの報告に似ているが言葉の遅れを伴わない子どもたちを報告しました。
レオ・カナーは世界で初めての児童精神科医とされています。彼が報告した「早期幼児自閉症」は、知的遅れを伴うものであり、のちに「カナー症候群」と呼ばれることとなります。
ハンス・アスペルガーの報告した症例は、のちに「アスペルガー症候群」と呼ばれることになります。しかしドイツ語の論文であったため、第二次世界大戦中であった当時はあまり注目されることはありませんでした。
混乱期(1943年~1960年代)
自閉症が後天的な障害であるという誤った考え方は、マイケル・ラターが1960年代後半に仮説を発表するまで、なんと約20年も続きました。彼は、自閉症が先天性の脳機能障害であるという説(認知・言語障害仮説)を発表しました。
自閉症は母原性(母親の誤った療育態度が原因で発生する病気)とされ、自閉症児の母親を「冷蔵庫マザー」とまで呼び、愛情をもって子どもと接することで治癒することができると考えられていました。
そのため、絶対受容(子どもの気持ちや行動を全て受け入れる)や、抱っこ法(抱っこを促し、ASD児が持つ触れられることの嫌悪感を強引に矯正する)といった非科学的な誤った対応が横行しました。
自閉症の母原性は、日本でも長く尾を引く偏見となりました。残念ながら現代でも、ごくごく稀に「自閉症は母親の所為だ」という偏見を見かけます。とても悲しいことですが、ASD児の特性を受け入れられない社会と、その悲しさを母親にぶつけていたのだろうと思います。
現代では、絶対受容や抱っこ法は全く効果がないばかりか逆効果、さらに倫理的な面からも疑問視されるものとなっています。
サブカテゴリーの発見(1970年代~1990年代)
その後の研究で、自閉症に似た症状を示す状態が知られることとなり、1980年のアメリカ精神医学会の診断基準(DSM-Ⅲ)では「広汎性発達障害」という上位概念が作られました。1981年にはイギリスの精神科医ローナ・ウィングが「アスペルガー症候群」を発表し、大きな反響を呼びました。これはかつてのアスペルガー博士の考えを紹介した論文でした。
以後、知的・言語の遅れを伴わない自閉症の子どもたちへの理解や研究が飛躍的に前進します。1990年代には精神障害の診断基準にも、アスペルガー症候群や高機能自閉症(知的発達の遅れのない自閉症)など、自閉症のサブカテゴリーが取り入れられました。
現在でも「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」「広汎性発達障害」これらの言葉は社会に残っていますし、医師の診断でも見かけます。しかしそれらの違いが大きく取り沙汰されることはなく、同じ「自閉症」として扱われることが多いです。
スペクトラム概念の登場(2000年代~)
自閉症のサブカテゴリーが発見されるとともに、「自閉症はスペクトラム(連続体)である」という考え方が広まります。これは「自閉症の特徴は典型から軽微、全く特性のない人までが連続して存在している」という考え方で、「自閉症の境界線はとても曖昧なものである」という新しい概念でした。
これを受けて、2013年のDSM-5では自閉症のサブカテゴリーが廃止、自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害)と統一されました。
おわりに
さて今回は、歴史的側面に関して見ていきました。
初めて学んだ時、統合失調症などと比べ発見が比較的最近であること、しかし他の障害と同じくその近親者が迫害されてきたこと、現在はスペクトラムという新しい概念によって困り感を掬い取りやすい時代が来ていること、これらに驚き、悲しみ、嬉しく思いました。
これからの自閉症は、脳科学・心理学を中心とした、理解と支援の歴史になってゆくのだろうと思います。
また、その歴史が当事者、定型発達者、社会全体にとって良いものであれるよう、という想いを込めて、この記事を書いています。
ということで、次回からはASDの具体的特徴について見ていきます。
これからのASDの歴史が、輝かしいものでありますように!

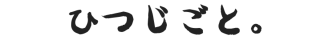
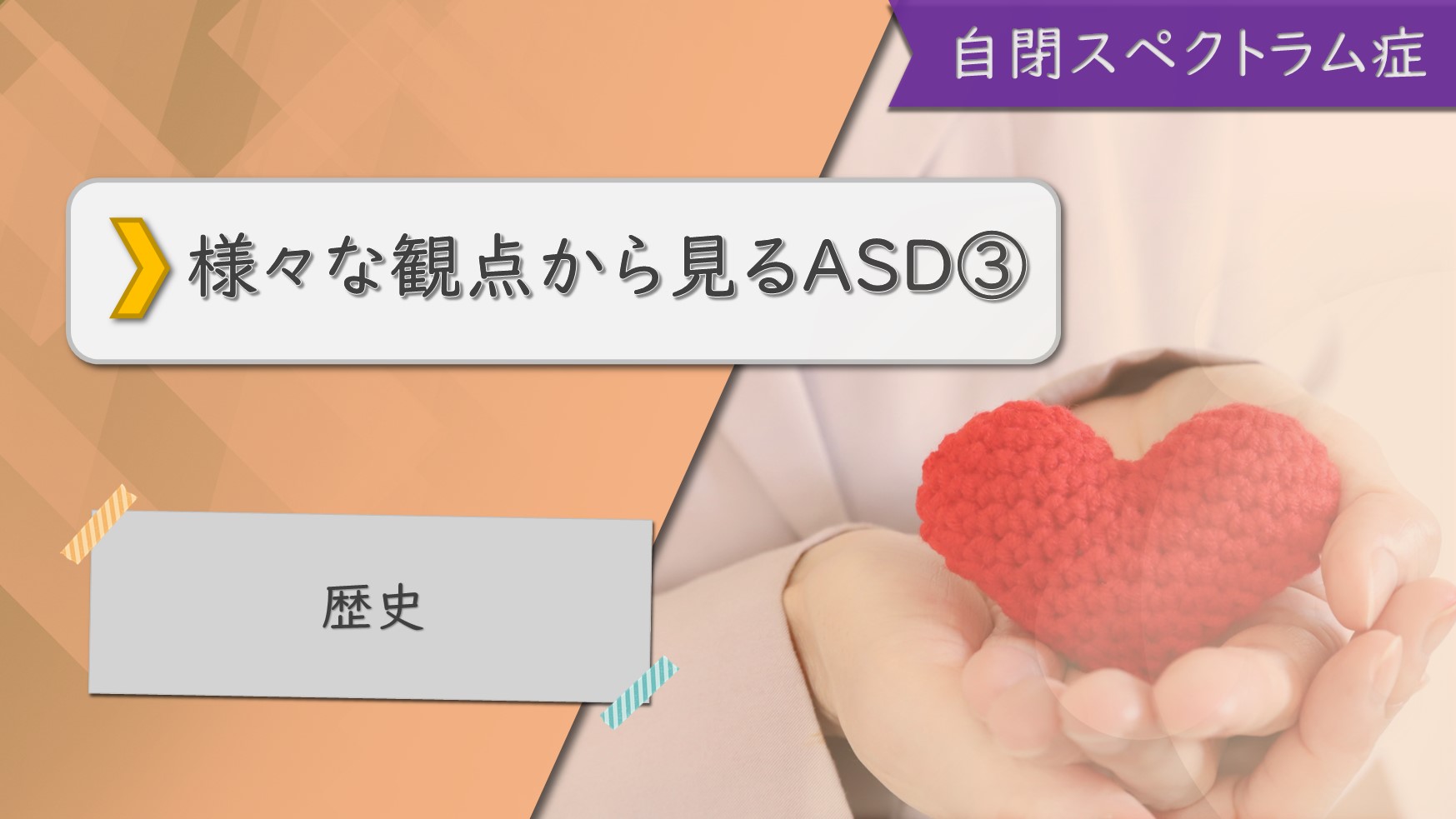
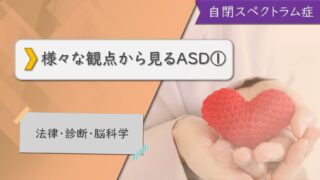
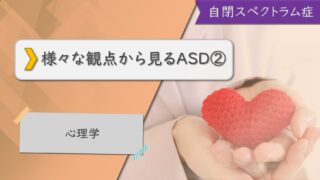
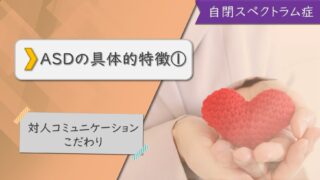
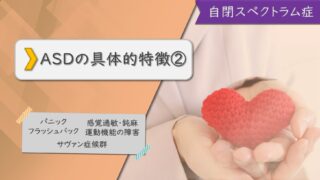
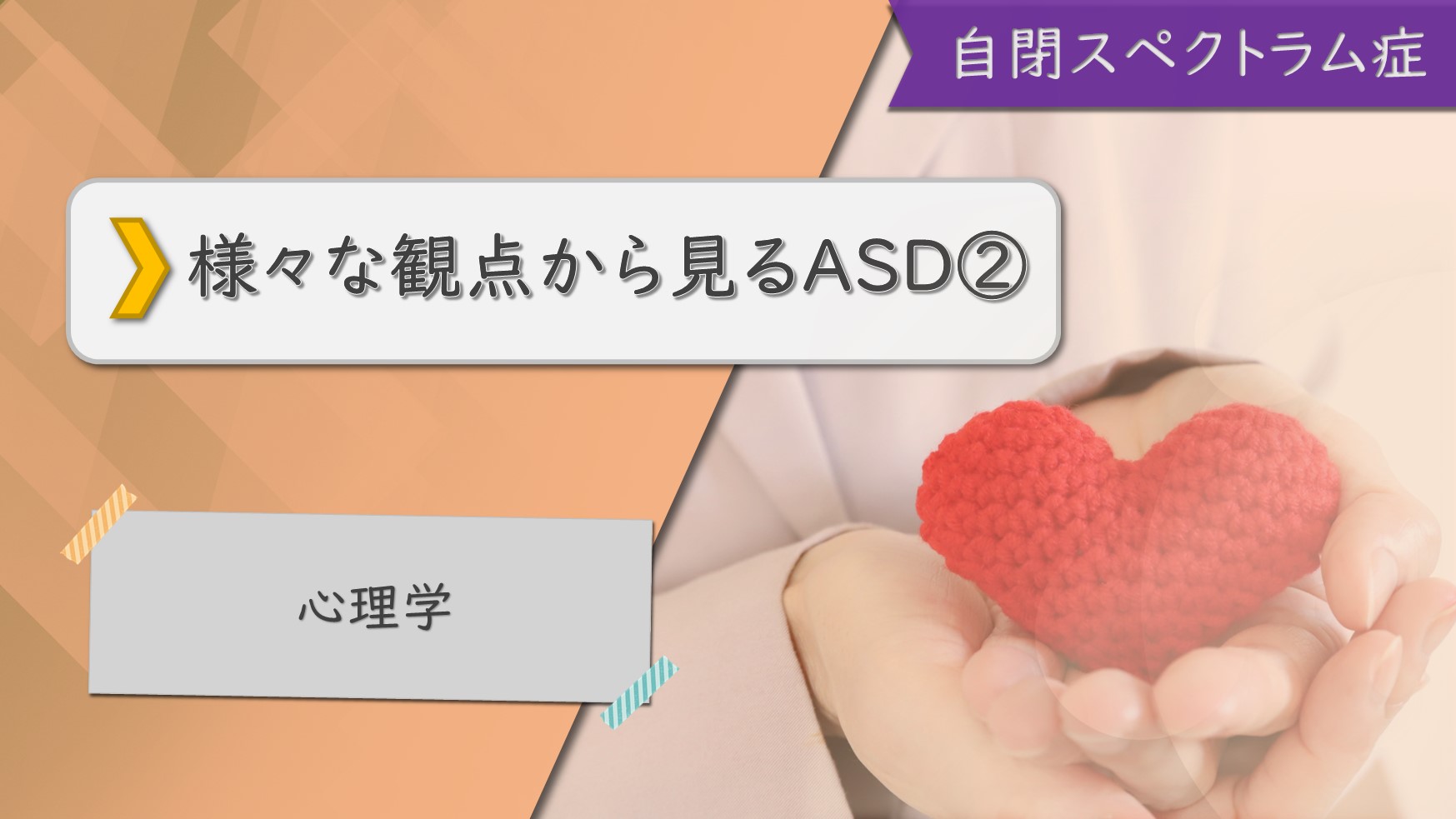
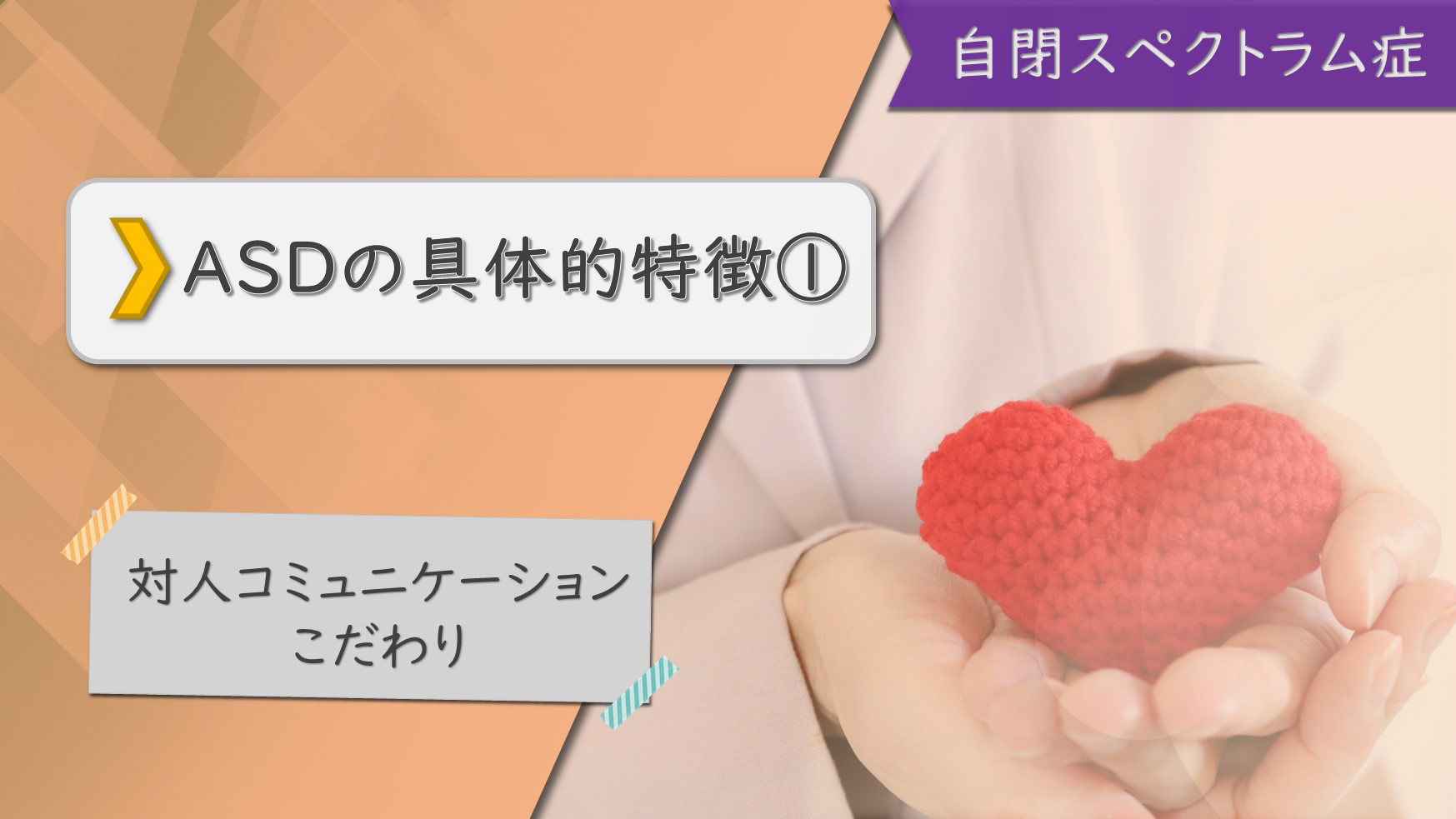

コメント