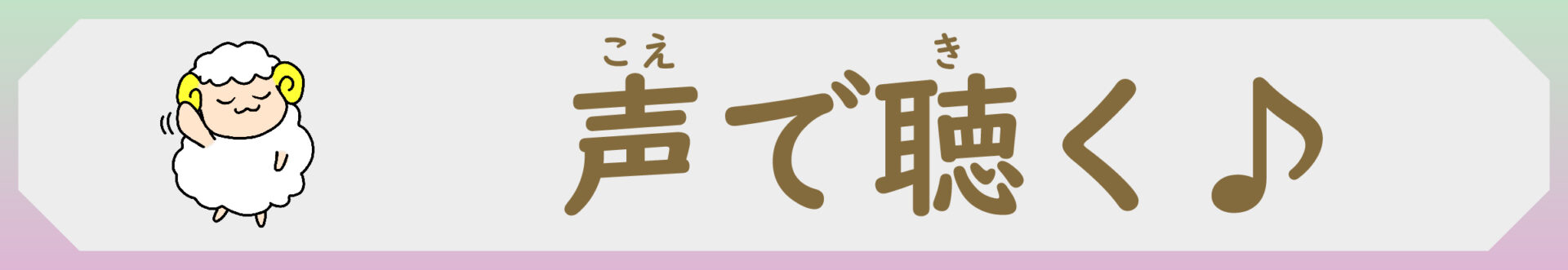
前世はネコ。
どうも、ひつじぃです。
はじめに
この記事では、自閉スペクトラム症(ASD)の具体的な特徴を、一つ一つ細かく見ていきます。
特に今回書く「パニックへの対応」は、非常に大事な内容になってきます。
保護者さん、教育・支援関係者さんに是非見ていただきたいなと思います。
前回までの内容の関連も含みますので、よろしければそちらも御覧ください。
それではれっつごー。
以後、自閉スペクトラム症を「ASD」、非ASD者を「定型発達者」と呼びます。

知っているだけで全然違うからね!
パニック
パニックとは
何らかの理由により自分の感情や行動がコントロール不能になり、混乱状態に陥ること。ASDの人はパニック状態になりやすい傾向があるとされます。パニックを引き起こす理由は様々ですが、ストレスの蓄積により情報の処理が困難になることが原因とされています。
他にも、好きな対象に興奮しすぎて行動の抑制ができなくなる、表面には表れにくいものの思考や感情が停止(フリーズ)してしまう「静的なパニック」も存在します。
パニック状態の例
・暴れだす、走り出す
・泣き出す
・ものを投げつける
・大声を上げる、暴言を吐く
・自傷行為をする
支援現場にいると、パニックには沢山遭遇します。その対応は後述させてもらいますが、大事なのは「思っているよりも『静的なパニック』が多い」ということです。
「こんにちは」と言われ、固まってしまう子もいます。学校では「なんで返事、挨拶をしないの」と叱られるそうですが、明らかに静的なパニック状態にありました。
こういった表面的な行動に大きく現れない状態は、とても見過ごされやすく、周りが気付くころには本人の困り感がとても大きくなっていることが多くあります。
とても簡単なことであっても「できるけどしない」のではなく「できない」状態にあるのではないか、という可能性を常に持って接する必要があります。
ASDのパニックの原因
パニックの原因は様々です。しかし必ず理由が存在し、その理由はパニック状態を引き起こすくらいの大きいストレスであるということ、それによって本人がとてもしんどい思いをしているということをしっかり念頭に置いて、解決へ導く必要があります。
【パニック状態を引き起こす原因の例】
・不快な感覚
・こだわりを否定された
・何が起こるかわからない新しい場面
・フラッシュバック(過去のストレス場面を思い出すこと)
・過度の疲労、体調不良
・強すぎる感情体験
繰り返しになりますが、パニックには必ず原因があります。
そしてパニック状態の間は、本人はとてもしんどい状況にあるのです。
フラッシュバックのように、パニックの原因が「今」にない時もありますが、その理由を探り、本人と一緒にパニック回避の方法を考えていくことがとても大切になります。
以前、突然パニックが現れた子の原因が「過度の疲労」だったことがありました。
しかし親御さんより「本人は疲れていないと言っている」、でも疲れているようには見えると。
どういうことかというと、ハイコントラスト特性や後述する感覚鈍麻にも関わってくるのですが、「体調不良がよく分からない」というASDの特性が絡んでいました。
体調が悪くても、体温計で熱を測って数字が出るまで「体調不良である」ということが分からないのです。こういったケースは多くあり、集中力の低下や特性が強く現れる原因となることがあります。
パニックへの対応
支援・対処法の記事で説明しています。こちらへどうぞ。
フラッシュバック(タイムスリップ現象)
フラッシュバックとは
フラッシュバックという言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。これはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の用語であり、「傷ついた体験に関連した記憶が、突如鮮明によみがえる」ことを指します。大きなストレスを伴うため、パニックに繋がることもあります。
そしてASDの人たちにも同じような現象が起こることが知られており、あまりに生々しい体験から「タイムスリップ現象」とも呼ばれます。
面白いことなのですが、ASDの人のフラッシュバックは「楽しいこともよみがえる」と言われます。パソコンで動画を見ていたASDの子が「映画を見ていた時にタイムスリップしてた!」と教えてくれることもあります。楽しいことだけフラッシュバックして欲しいものですね…。
ASDのフラッシュバックの原因
ASDの人は、脳の構造的にフラッシュバックが起こりやすいとされています。しかし、その原因に関して明確には分かっていません。何らかの脳機能障害、特に脳の記憶に関するメカニズムが影響しているのではないかと言われています。
近年、PTSDと自閉スペクトラム症の線引きが行われています。フラッシュバックとタイムスリップ現象もその一つです。
なぜかというと、PTSDは「治療すべき精神疾患」であるため、似た現象が現れるといえども区別する必要があるのです。
感覚過敏・鈍麻
感覚過敏・鈍麻とは
ASDの人たちの中には、特定の刺激に対して過敏に反応したり、逆に非常に鈍感であったりします。
これらは意外にも最近判明したことで、当事者が声をあげ始めたことにより少しずつ研究が進んでいます。
DSM-5からはASDの診断基準にも入っていますが、感覚過敏・鈍麻の詳細に関しては「聴覚情報処理障害(APD/Lid)」が新しく見いだされたりと、現在進行形で研究が進んでいます。
【感覚過敏の例】
・聴覚過敏
特定の音がしんどい
大きな音、突然の音でパニックになる
・視覚過敏
蛍光灯の光がまぶしい
色がまぶしくて目が痛い
・味覚過敏
通常判別できないくらいの味の違いに反応する
・嗅覚過敏
特定の香りで鼻が痛くなる
【感覚鈍麻の例】
・痛覚鈍麻
画鋲を踏みつけても気づかない
・自己モニタリングの困難
満腹・空腹の感覚が分からない
・疲労度が分からない
・自分の感情に気づけない
感覚過敏・鈍麻への対応
感覚過敏・鈍麻は、「人の感覚であるため比べることが難しく気づきにくい」という難点があります。
ずっと会話が難しいとされてきた人が、聴覚過敏で人の声がうまく聞き取れていなかっただけ、ということさえあります。
また疲労度がうまく把握できないために、元気で遊んでいたのに突然倒れる、ということもあります。
これらの感覚過敏・鈍麻は、直接「生きづらさ」に繋がる一方、対策も比較的簡単であり対策によってできることがたくさん増えた、というケースも多いです。
最終的には本人が自身の感覚過敏・鈍麻を自覚して対応できるようになることを目指しますが、周囲の人が「もしかしたら」を常に考えて接し、フォローを行っていくことが大切かと思います。
運動機能の障害
ASDの運動機能の障害とは
ASDの人たちの中には、身体を動かすことが極端に苦手な人がいます。これは身体が感じる情報(手足の動きや平衡感覚など)を脳が処理してうまく運動につなぐこと(固有感覚)に困難があるとされています。
また、腕や足を動かしたり見たりして初めて存在を実感できる、という独特な身体感覚(ボディイメージ)を持っていることもあります。
運動機能の障害には、粗大運動(身体を大きく動かす運動、歩く走る等)と微細運動(身体小さく細かく動かす運動、紐結び折り紙等)の両方が含まれます。
運動機能の障害への対応
身体感覚(ボディイメージ)を育むこと、アイテムに頼ること、これらが大事なことかなと思います。
ボディイメージを育む
ボディイメージでは、両腕を広げた長さを測ったり、新聞紙の上に載って足元に丸を書いて切ってその穴を通ったり…。ゲーム形式で沢山取り組めるものがあります。
長さの感覚が弱い子には、両手で30cmを作ってもらって定規で修正し、部屋の中から30cmに近いものを探してくる、というゲームも行いました。
語り始めたらキリがありませんので、また後日、記事にしたいと思います。
アイテムに頼る
アイテムでは、こちらの書籍がとてもとてもおすすめです。
特別支援学校の先生である佐藤義竹さんにより書かれた本で、「食べる」「身体を洗う」から「カッターを使う」「パニック時に使う」などなど…紹介されている道具の数はおよそ100。金額から購入先、良いところや使い方まで、すべてを網羅しています。
ひつじぃ激推しの一冊なので、色々調べてもらう前にこの本を購入して欲しいと思います。
個人的に、すべての教育機関・支援機関に置いて欲しいです。
序文から、引用させていただきます。
大切なのは「(手だての活用を通して)~できる」という視点です。児童生徒の「~が難しい」という実態から、具体的な手立ての活用を通して、「できない」から「できる」に変わるということです。
2023 小学館 『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』 はじめに
注意点
人によっては「うまく身体を動かせない」ということに強く劣等感を感じていることもあります。
定型発達者であっても、得意苦手はあるものです。先天的な脳構造の違いからくる難しさと考えられる以上、「できるようになる」よりも「うまく付き合う」ことが大切になってくるのではないかと思います。
サヴァン症候群
映画「レインマン」で有名となった「サヴァン症候群」。映画の中では、落ちたマッチ棒の本数を一瞬で当ててしまうなど、超人的な能力が紹介されています。
広義・狭義ありますが、基本的には「特定の分野で並外れた能力を発揮する」という特性を指します。
ドラマ等で取り上げられがちですが、ASDの人のごく一部、それも障害深度が深い人に見られることが多いです。
サヴァン症候群は、「自閉症は特別な能力を持っている」と、やり玉にあげられているのをたまに目にします。
私の友人の話ですが、大きい本屋でバイトをした際「(ゆっくりでいいから)本がどこにあるかとか覚えてね」と言われ、一日で全ての本の場所・題名・著者・出版社等全て覚えてしまったという例があります。
周りからは「すごい能力だね!」と言われるのですが、本人はそれにより恐ろしく疲弊し、体調管理もままなりません。情報はどんどん頭に入ってきてしまうため、夜眠れないことも少なくないそうです。
「特別」というのは、「周りと違う」ということです。その違いから羨まれることもあったり、自信になったりすることもあったりと良い面もあれば、本人の負担や思わぬ副作用?で苦しむことも少なくないことを、忘れないようにしたいと思います。
おわりに
今回は、ASDの具体的特徴のうち、パニック、フラッシュバック(タイムスリップ現象)、感覚過敏・鈍麻、運動機能の障害、サヴァン症候群について駆け足で見ていきました。
しかしこういった知識があると、感覚過敏・鈍麻に気づいて可能性を広げられたり、「よくぶつかったり転んだりする」ことからボディイメージの弱さに気づいて早期に身体を動かす練習を始められたりと、とても良いことが沢山あります。
私が常々思うことは、「家庭・教育・支援・医療…」といった各分野の人たちに「適切な知識がない」ために生きにくさが何倍にも膨れ上がってしまっている、ということです。
知っているか、知らないか。ただそれだけのことが、人生すら大きく左右してしまう。
とても悲しいなと思うと同時に、知ってもらえればもっともっとお互い生きやすくなる、と確信もしています。
「習うより慣れろ」という言葉がありますが、発達障害関連に関しては、まず第一に知識。これは私がぺーぺーの新米支援員だったころに、信頼できる方々から耳が痛くなるほど言われ、今改めて痛いほど身に染みています。
「知識があればもっとラクな人生を伝えられた…」という場面が山ほどあるのです。
そして、今の私もまだまだまだまだ勉強が足りません。相手は人間なので、一生足りません。
これからも私と一緒に勉強し、沢山のユニークな人々と交流していきませんか。

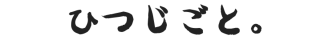
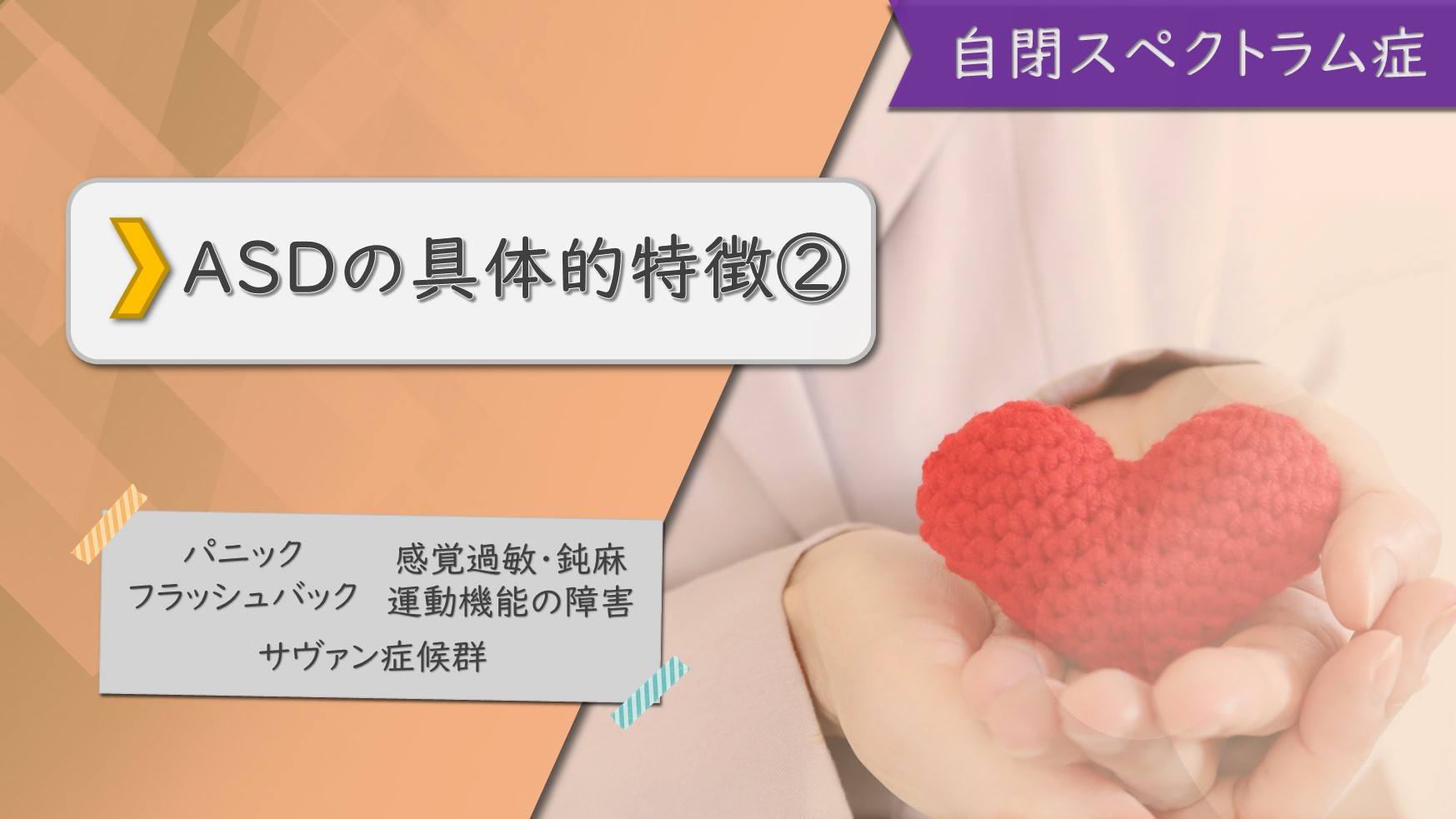
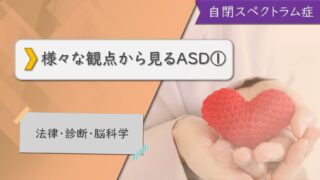
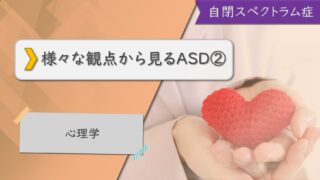
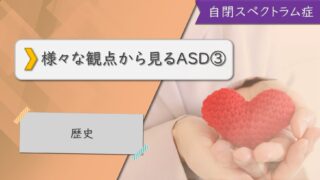
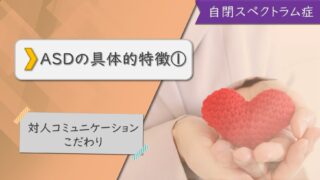
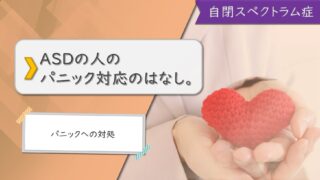
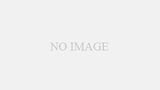


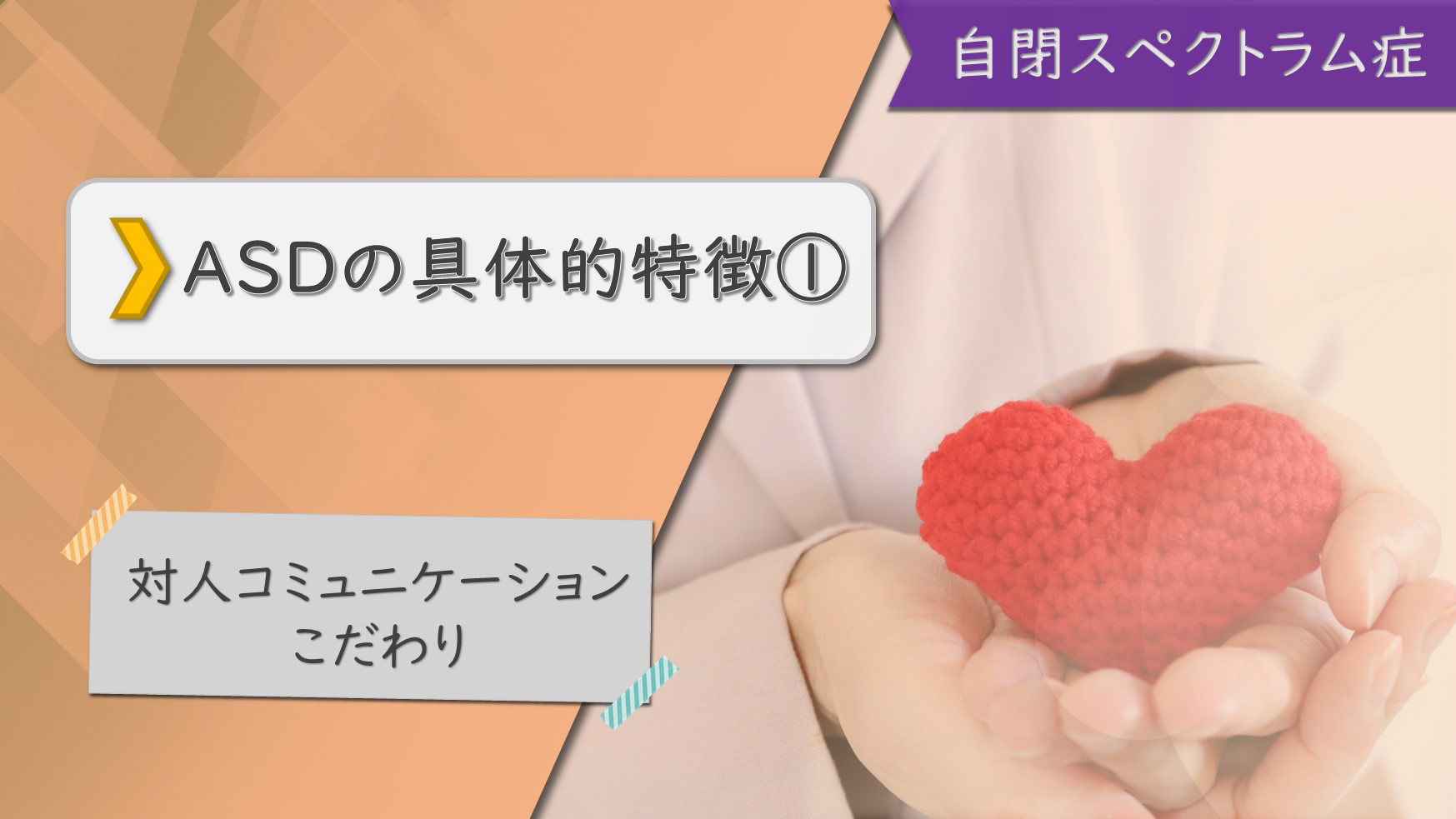
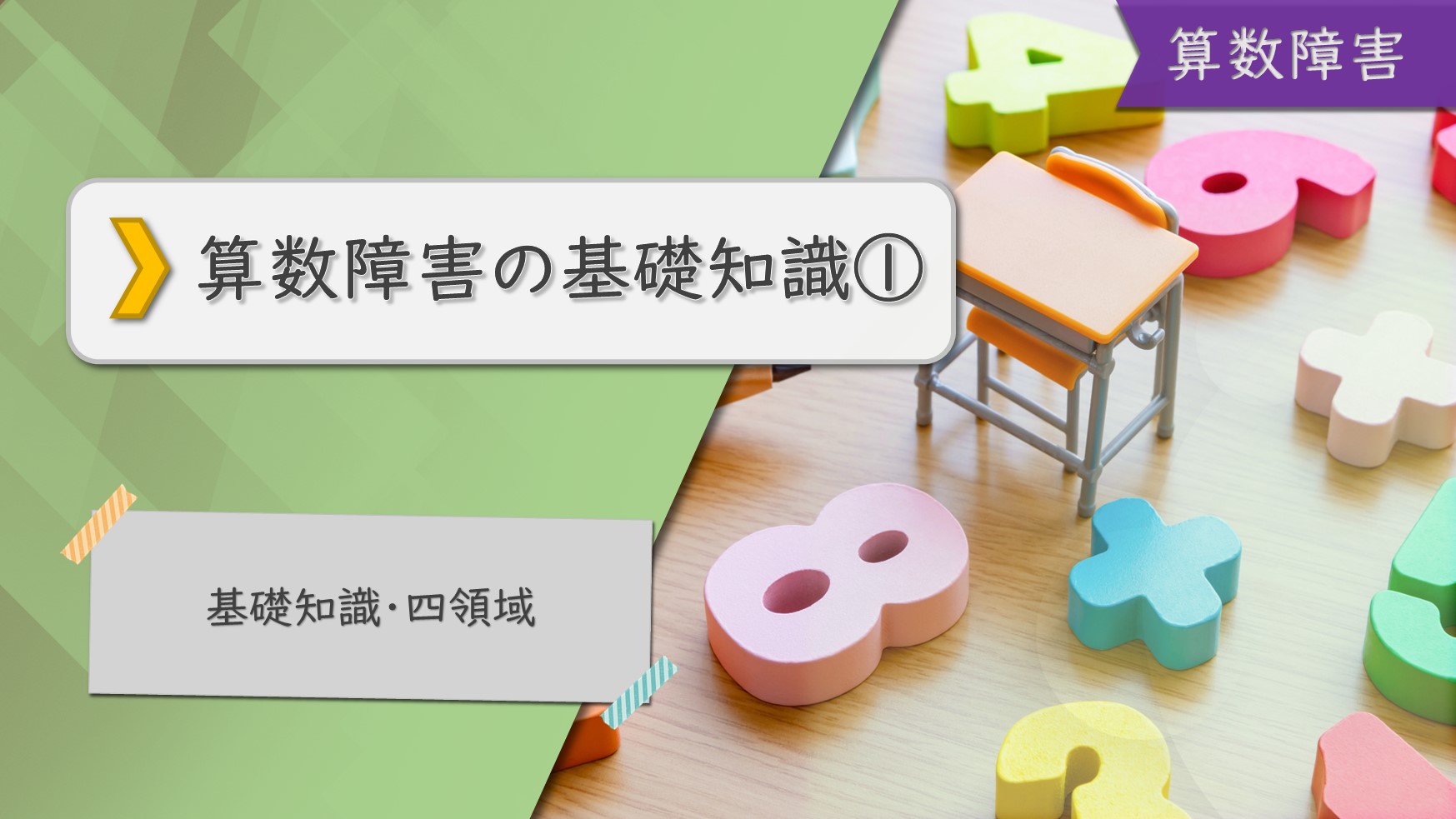
コメント