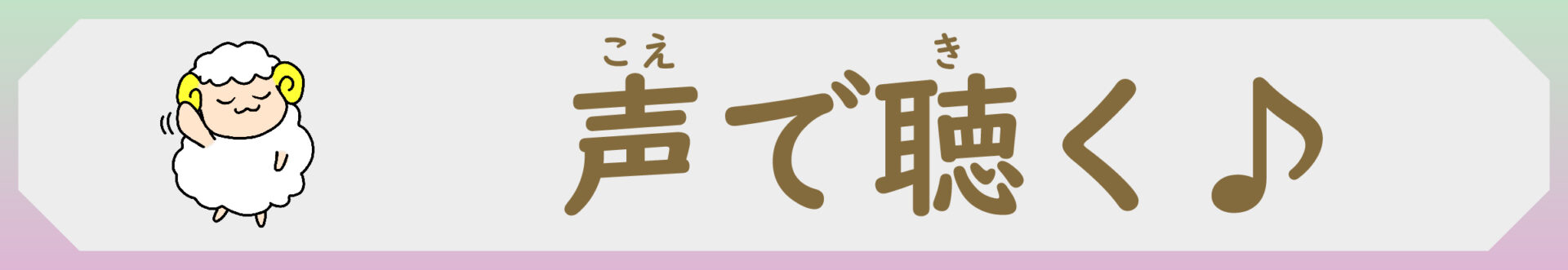
どうも、子どもたちとのドッヂボールに夢中になりすぎ、全身筋肉痛のひつじぃです。
「同時処理」「継次処理」とは?
前回の記事でテストをした「認知処理様式」ですが、「同時処理」「継次処理」という二つの種類がありましたね。
まず辞書的に説明します。
【同時処理】
情報を全体的・空間的なまとまりとして考え、関係性を見出し処理する力。
言い換えると「複数の情報を同時に処理しながら一つ一つを理解する能力」。
【継次処理】
情報を一つずつ時間的・順序的に分析し、手順として処理する能力。
言い換えると「複数の情報を一つ一つ処理しながら全体を理解する能力」。
それでは、詳しく説明していきます。
例えば料理なのですが、完成した形や味をイメージするでしょうか、レシピから調べるでしょうか。
前者の方は、全体の形や味から、使う食材や調味料、料理工程を考えるかもしれません。
後者の方は、レシピから一つずつ、使う食材や調味料、料理工程を追っていくかもしれません。
これが、「同時処理」と「継次処理」です。この場合、前者が「同時処理」寄り、後者が「継次処理」寄りとなります。
全体をイメージし、そこから関連性を見つけていくのが同時処理。
例えば、歴史の出来事を覚える際「この出来事があったからこの人はこういうことをして、それによってこの出来事が起こって…」と関連性を重視した覚え方は「同時処理」の力を使っていることになります。
一つずつ手順を追って全体を完成させるのが継次処理。
例えば、同じ歴史の出来事を覚える際「この年代に起こった出来事は他に〇〇と●●で、順番はこうで…」と順序と時間軸を重視した覚え方は「継次処理」の力を使っていることになります。
では、なぜこの「認知処理様式」が大切なのでしょうか。

同じ人間でも、考え方に得意苦手があるんだね!
認知処理様式の得意苦手の偏り
前回の記事で、簡単なテストを二つしてもらいました。
その意図をお伝えします。
一つ目のテストは「あなたが無自覚に選ぶ傾向にある認知処理様式」を知ること。
二つ目のテストは「本当にあなたに合った認知処理様式」を知ること。
このテストには、学習困難を抱えていない人でさえ、個人差が大きく出ます。
そうです。
この認知処理様式の得意苦手に大きな偏りがあると、学習方法によってはほとんど効果がないなんてことが起こります。
この「認知処理様式の得意苦手の偏り」のことを、認知処理特性といいます。
同時処理が得意な人は「同時処理優位」、継次処理が得意な人は「継次処理優位」といいます。
知能検査の中でも学習特性を測ることを得意とするテストに、カウフマン博士によって考案された「K-ABCⅡ」という検査があります。この検査では「同時尺度」「継次尺度」という名前で結果が出ます。
学習に関する能力は、神経心理学者の祖・ルリア(Luria, A.R.)によって「プランニング」「注意」「符号化」の3つに大別されました。さらに後に、「符号化」の中の認知処理スタイルには「同時処理」と「継次処理」の二つに分かれることが判明しました。
この「同時処理」「継次処理」の得意苦手に関しては、最近ようやく少し注目されてきたように思いますが、まだまだ知名度は低いままに感じます。
認知処理特性、得意な認知処理様式は「頭の中の利き手」ともいえる、大事なものなのです。

右利きなのにあえて左手で文字を書いたりしないよね?
学習と認知処理特性
さて、皆さん前回記事のテストの、一回目と二回目の結果はどうでしたか?
「一回目に継次処理で覚えたけど、二回目の同時処理の方が覚えやすかった」という人は多いのではないでしょうか?
それはなぜか。ひつじぃは「学習量が多くなればなるほど作業的になり、教育全体が継次処理に傾くから」だと考えています。要は、家庭・学校・塾その他の教え方・学習自体が、継次処理寄りなのです。

そういえば、数学の公式を当てはめることはしたけど、その公式がなんでそうなるのか教えてもらってないかも…!
先ほど「学習方法によってはほとんど効果がないなんてことが起こる」と書きましたが、この現象がまさにここで発生します。
「同時処理優位」の人は、他の人に何か教える際、無自覚に「同時処理優位」の方法を教えます。
「継次処理優位」の人は、他の人に何か教える際、無自覚に「継次処理優位」の方法を教えます。
それは「うまく理解できないけど、この学習方法が正解」と信じ込ませてしまうことになるのです。
ここでできることは一つ。「認知処理特性について知り、自分の認知処理特性を把握する」ことです。
支援者であれば、見立ての中に認知処理特性の視点がなければなりません。その見立てができていないのであれば、何かを教える以前の問題なのです。
利き手が左手なのに、無理して右手で文字を書かせているようなものなのです。
生活と認知処理特性
生活の中でも、認知処理特性は現れます。
最初に例に出した料理は、分かりやすいですね。
ちなみにひつじぃはバリバリの同時処理優位なので、実はレシピを読みながら料理をする・買い物をするのが本当に苦手です。もう無理といっていいくらいのエネルギーを使う作業です。
なので、あらかじめレシピを読み込み、頭の中でイメージしてからでないと料理ができません…大変すぎて、嫁さんに任せてしまっています。苦笑
ここで「レシピを見ながら料理って同時処理では?」と思う方もいるかもしれません。
当たりであり、はずれでもあります。
理由は、「同時処理能力」と「物事を同時にこなす(マルチタスク)」の能力はまた別だからです。
なので、「マルチタスクが苦手だから私は継次処理かな…」という訳ではないのですね。
逆に、片付けは得意です。片づけた後の全体のイメージをもって、モノの整理ができます。
しかしその方法は、「同時処理優位の人向け」の片付けです。では「継次処理優位の人向け」はどうしましょうか?
ひつじぃ、考えました。継次処理に関しては自分の苦手な認知処理様式をイメージして考えたので「私には合わない…」という場合があったら許してください。
1. 部屋を片付けたらどうなるか、イメージ図を描く
(どれをどこに片付けるかもイメージしてもいいかも!)
2. 実際に片付けを始め、片付けきれないものが出てきたら「この一年間で使ったか」を考える
3. 使ってなかったらゴミ箱にポイ!使っていたら、他に「この一年間で使っていなかったもの」を見つけよう!
4. 全部片付いたらおしまい!
1. 二つ箱を用意し、必要なものと必要でないものを一つずつ考え、それぞれの箱にまとめておく
2. 「必要でないものの箱」の中身をゴミ袋に移し、「必要なものの箱」から一度モノを全部出す
3. 今度は「この一年間使っていたかどうか」で、それぞれの箱にまとめておく
4. 「この一年間使っていなかったものの箱」は奥の方に、「この一年間で使ったもの」は手前にしまう
5. 全部片付いたらおしまい!
…という具合に、認知処理特性一つで生活のあらゆる方法が変わってきますね。
ということは、です。
認知処理特性を考えれば、もっとラクに生活が送れるかもしれない!
沢山考えるのはエネルギーを使いますので一つ一つ取り組むのが良いかと思いますが、意外とラクになったり、困りごとが改善したりします。
是非毎日1分だけ、考えてみてください。

ひつじぃは、部屋の掃除の仕方(考え方)を変えたらラクになったよ!
認知処理特性の多様性
この記事でお伝えしたいことは、教育への不満でもなく、苦手を克服する方法でもありません。
もっとラクに生きるために、認知処理特性を活用しよう!
ということです。慣れてきたら、相手の認知処理特性を把握できると、コミュニケーションから教育まで結構うまくいきますよ。
認知処理特性は、人によって大きな個人差があります。時にはバランスよく両方の能力を持ち合わせている人もいますが、ひつじぃのように同時処理優位で継次処理はからっきしだったり、その逆の人もいます。
今、世の中は多様性を認める社会風潮が生まれています。
しかし、「多様性を認める」ということは、他人よりもまず自分を知らねばなりません。
見えない部分の多様性まで認められる社会に、少しでも貢献出来たら嬉しいですし、何よりこれを読んでいただけた方々の今後の人生、今の生活がラクに楽しいものになってくれることを心から願います。
それでは、次回はとうとう「認知処理特性の主要五教科への具体的な応用・工夫」をお届けしたいと思います。
それではひつじぃも、同時処理的な方法で苦手な洗濯に立ち向かってきます!!
ではまた次回お会いしましょう。


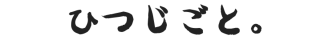
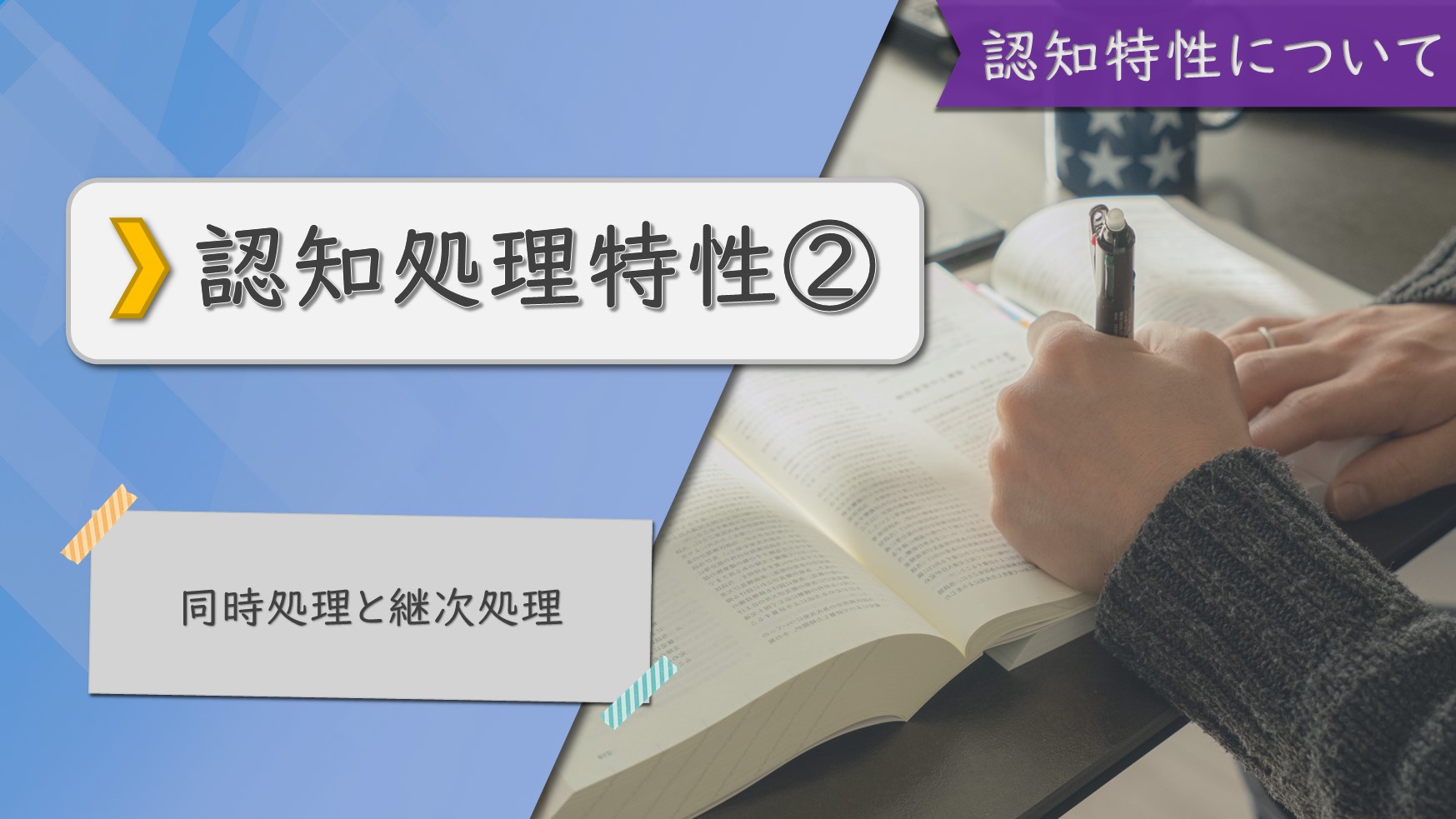

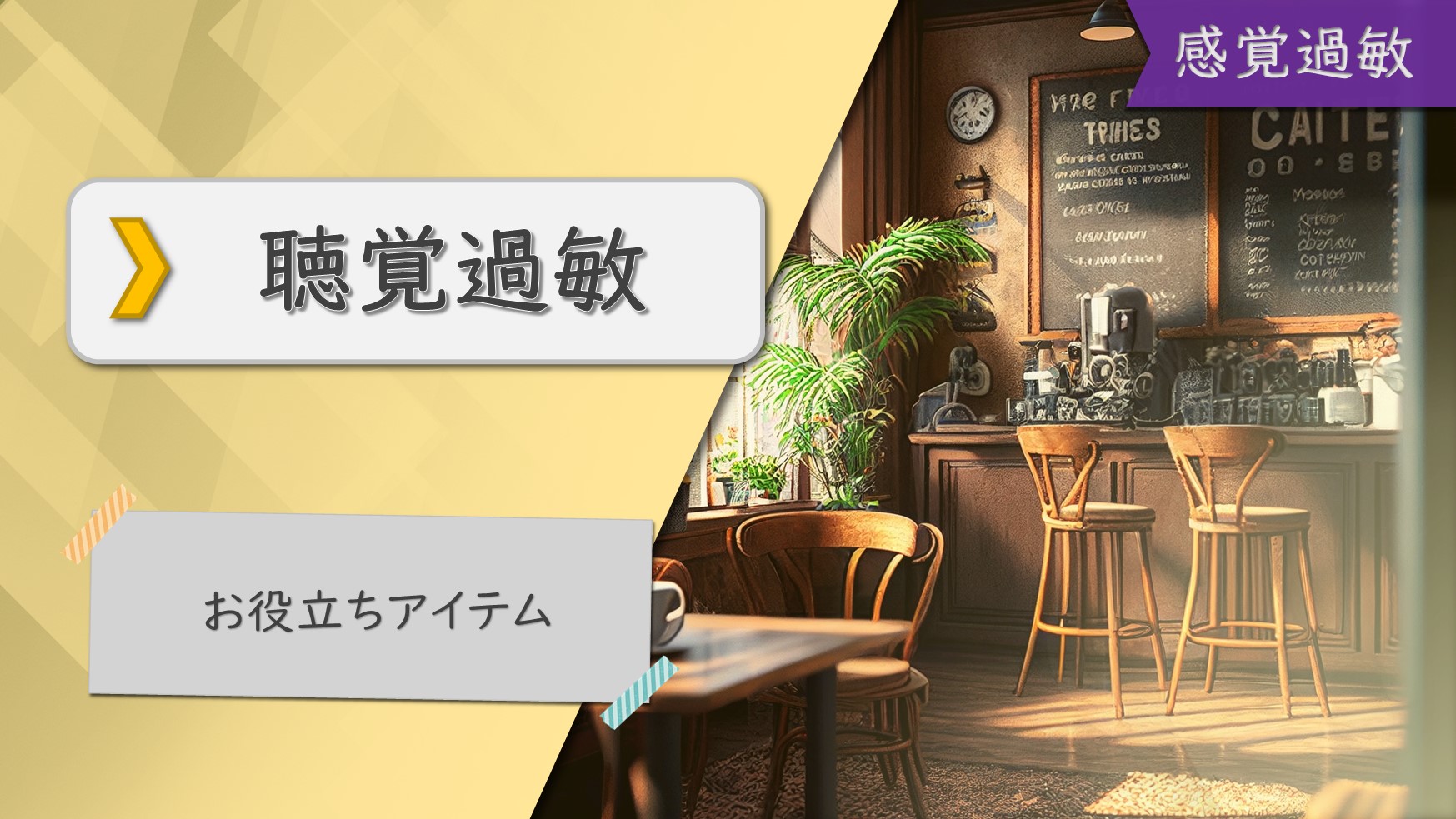
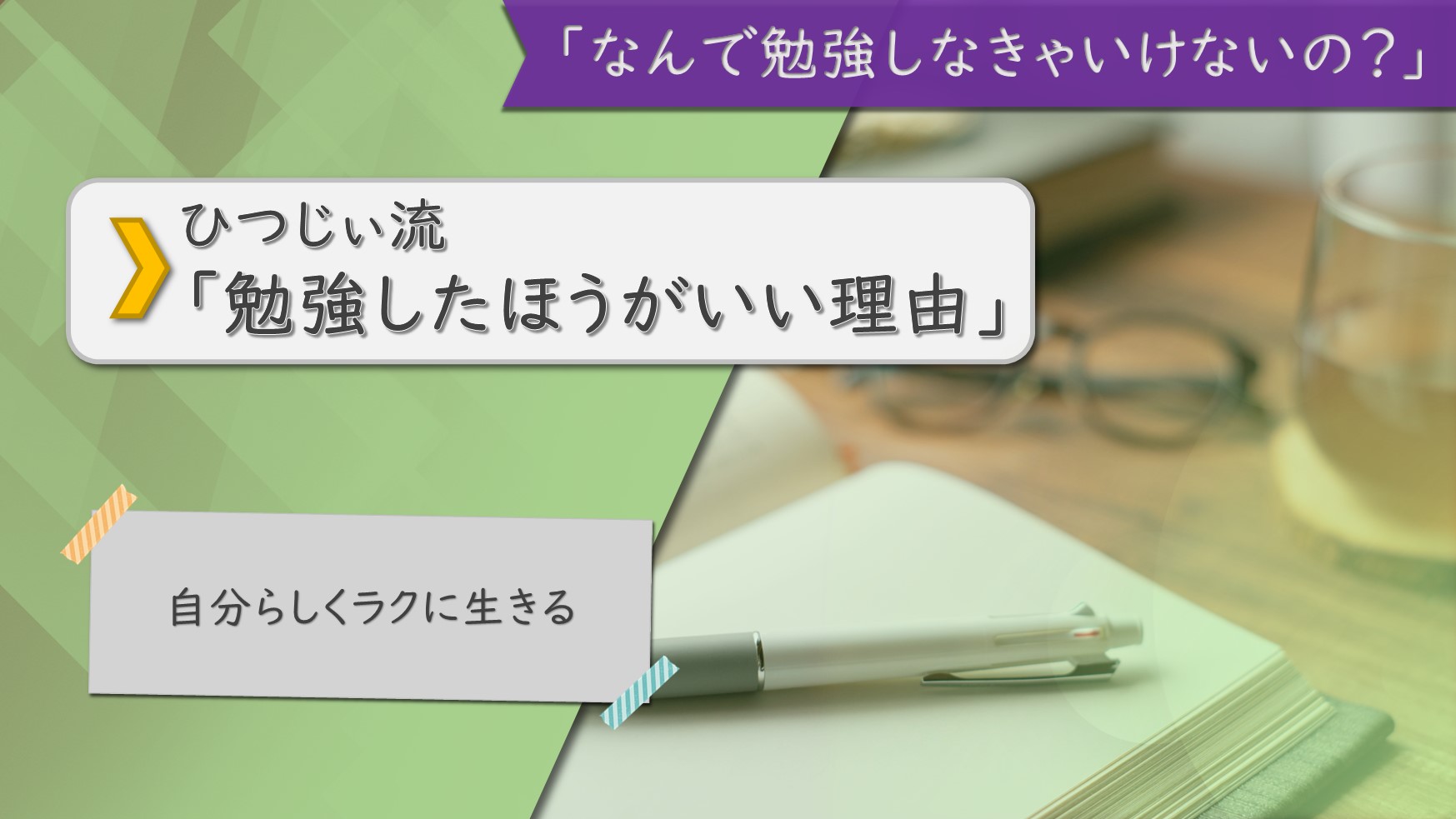

コメント