聴覚過敏とは?
今回のテーマは「聴覚過敏」。発達障害と一緒に持って生まれてきやすい「機能的障害」である「感覚過敏」の一つです。
まず、以下の二つの動画を見てください。その際、イヤホンかヘッドホン、またはスピーカーを用意していただけるとその後の話が分かりやすくなります。
いかがでしたでしょうか。
2つ目が、聴覚過敏を持っている人が体験している音の世界の、一例の参考です。
子どもたちの体験談や支援的な知識を参考に、聴覚過敏の疑似体験動画を作ってみました。人間の「目に見えない感覚の違い」であり、どういう音に過敏性を示すかは人それぞれですので、あくまで想像の中の一例となります。
2つ目の動画で、相手の声が聞き取れましたでしょうか。この場所に居続けたいと思いますでしょうか。
聴覚過敏の状態としては、以下のような形があります。
・反響・・・耳鳴りが頭の中に響く。
・話し声・・・子どもや女性の高い声、電話の声などが聴きとりづらい。
・騒音・・・ゲームセンターやボーリング場、繁華街、人混み、駅のホームなど、騒がしい音が不快に感じる。
・接触音系・・・食器と食器がぶつかる音やドアを閉める音などが不快に感じる。
・執着系・・・静かなときに聞こえる音が気になってしまう。時計の秒針の音や、キーボードをタイプする、マウスを操作する音などが不快に感じる。
未だはっきりとした定義はなく、人間の感覚の課題である以上、他の人と状態を比較することも困難です。そのため、ずっと気づかなかったというケースも多くあります。
さらに、なぜこのような「感覚の違い」が発生するのかは、現時点では詳しく分かっていません。
そして、有効な治療法もありません。人間の感覚ですからね。
さて、この聴覚過敏によって、どんな困りごとが発生してくるのでしょうか。
近年、従来の聴覚過敏の中の『「聞こえている」のに、「聞き取れない」、「聞き間違いが多い」など、音声をことばとして聞き取るのが困難な症状』を「聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder: APD)」として定義し、診断基準の確立を目指す研究がスタートしています。海外では「Listening difficulties:LiD」と呼ばれることが多く、これを「聞き取り困難症」と称し、従来のAPDをLiD/APDとして表記しています。
日本での認知度は低いままですが研究は進んでおり、NHKに取り上げられるなど広く知られる兆しを見せています。
まだ正式な診断基準の確立を目指している段階とのことで、この記事ではタイトルとコラムに名前を出してご紹介させていただきます。
今後さらなる研究の進歩と、広い社会認知を期待します。
【参考】
聞き取り困難症・聴覚情報処理障害(LiD/APD)
当事者ニーズに基づいた聴覚情報処理障害の診断と支援の手引きの開発
聴覚情報処理障害の症状を示す小児の学習支援のための検査法および補聴技術の開発
公式ホームページ
https://apd.amed365.jp/about-apd/index.shtml
聴覚過敏は何が困る?
聴覚過敏は「聴覚情報処理の困難」とされます。聴覚情報処理能力とは、音を聞く力である「聴力」とはまた別に、聞こえた音声を適切に処理して理解する能力です。この力に困難がある場合、「音を聞く力は正常なのに、聞こえにくい」という状態になります。
具体的には、音声を言葉として認識することが難しい、音が同時に聞こえると必要な音だけを拾いとるのが難しい、聞こえた音が違う音に聞こえる、といったことがあります。
その結果、「言葉を話す・認識する」ということにも困難が生じる場合があります。
また、特定の周波数・音量・タイミングの音を過剰に受け取ってしまうといった困難が生じる可能性もあります。
こういった様々な聴覚過敏の状態の中で、最も見逃しやすく隠れた困りごとに繋がりやすいのが「騒がしいところが苦手」といったものです。
それではその状態に焦点を当てながら、支援法・対処法を考えてみましょう。
人間の目には「焦点を合わせる」機能があります。実は耳にもその機能があります。これを、『カクテルパーティ効果』と呼びます(1953年にイギリスの認知心理学者のコリン・チェリーにより提唱、「音声の選択的聴取」「選択的注意」とも言われる)。
「ざわざわしたところで人の声が聞こえにくい」現象はカクテルパーティ効果が弱いことによって起こるのか、専門の方に質問したのですが、答えは「現時点では判明していない」「明確な定義がなく研究段階」とのことでした。
そうすると、ADHDの「注意の選択困難」が聴覚情報にも適用され、それが聴覚過敏的困難に繋がらないかと思ったのですが、これも研究段階とのことでした。
さらにASDの「情報過多」がどう関わるのか、これも研究段階…。今後10年で聴覚過敏の研究は進みそうですね。
支援法と対処法
繰り返しになりますが、まず大前提として「聴覚過敏の明確な治療法はありません」。
聴覚過敏の中には、自律神経の乱れによって引き起こされるものがあり、そちらに関しては治療が可能です。また生まれつきのものであっても、服薬や生活・環境調整で改善することがあります。
そのため、支援法・対処法の方向性としては「どれだけラクに過ごせるか」となります。
基本的には本人の能力の底上げを目指すボトムアップではなく、環境や道具によって特性を補うトップダウンの支援・対処が中心になります。
① 環境調整
一番先に考えるべき支援・対処です。例えば学校の教室でざわざわしているのがしんどいのであれば、別室登校をさせてもらう。
電車の音がしんどいのであれば、車やバスで移動する。
基本的には「行動する場所を変える」という形です。
② アイテムを使う
現在、聴覚過敏用のアイテムが存在し、一般で購入できるものも多くあります。
イヤーマフといった完全な音の遮断を目指すもの、専用のノイズキャンセリングイヤホンで雑音をシャットアウトすることを目指すものがメインになってくるかと思います。
専門の機器となると、人の声だけを判別して音を加工してくれる補聴器があるそうです。
聴覚過敏用のアイテムに関しては、次の記事にてまとめて紹介しております。
③ 心身を整える
自律神経の乱れによっても聴覚過敏が発生することは前述しましたが、「心身の疲れが障害特性を強くさせる」ことは広く知られています。
ただでさえ環境ストレスを感じやすい聴覚過敏の方は、自分のセーフゾーンを確保し、疲れたらそこで休む、といった対策がとても大事になります。
④ 医療機関にかかる/トレーニングを行う
日本の医学界でもまだ認知度が低いため診てもらえる病院は限られますが、日常生活を送るのが難しい場合、医療機関の力を借りるのも重要です。
聴覚情報処理障害(LiD/APD)として、自己診断・診断(相談)できる医療機関・どんな診断を行うのか・自分でできる工夫やトレーニング等が公式ページによりまとめられています。
とても有益な情報が得られます。是非一度ご覧ください。
聞き取り困難症・聴覚情報処理障害(LiD/APD)
当事者ニーズに基づいた聴覚情報処理障害の診断と支援の手引きの開発
聴覚情報処理障害の症状を示す小児の学習支援のための検査法および補聴技術の開発
公式ホームページ
当事者の方へ:https://apd.amed365.jp/party/index.shtml
聴覚過敏マークについて
2017年10月、「株式会社 石井マーク」より、「聴覚過敏保護用シンボルマーク」が無償公開されました。



他にも様々なタイプがあります。
聴覚過敏保護用シンボルマークはこちらから無料でダウンロード可能です。
http://www.ishiimark.com/symbol_usapin.html
この記事を読んでいただいた方に一つお願いがあります。
前述した支援法・対処法でも、うまく日常を送れない方もいます。
「見えない違い」を認められる社会へ一歩近づくため、この記事でも石井マークさんのサイトでも構いませんので、広く拡散をお願いしたいのです。
一人一人の理解と助けが今、必要とされています。
もちろん、理解と助けが必要なのは聴覚過敏だけではありませんが…。この記事が一つの助けとなれば嬉しく思います。
みんな違って、みんないい。
それでは、また次回お会いしましょう。

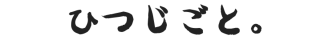
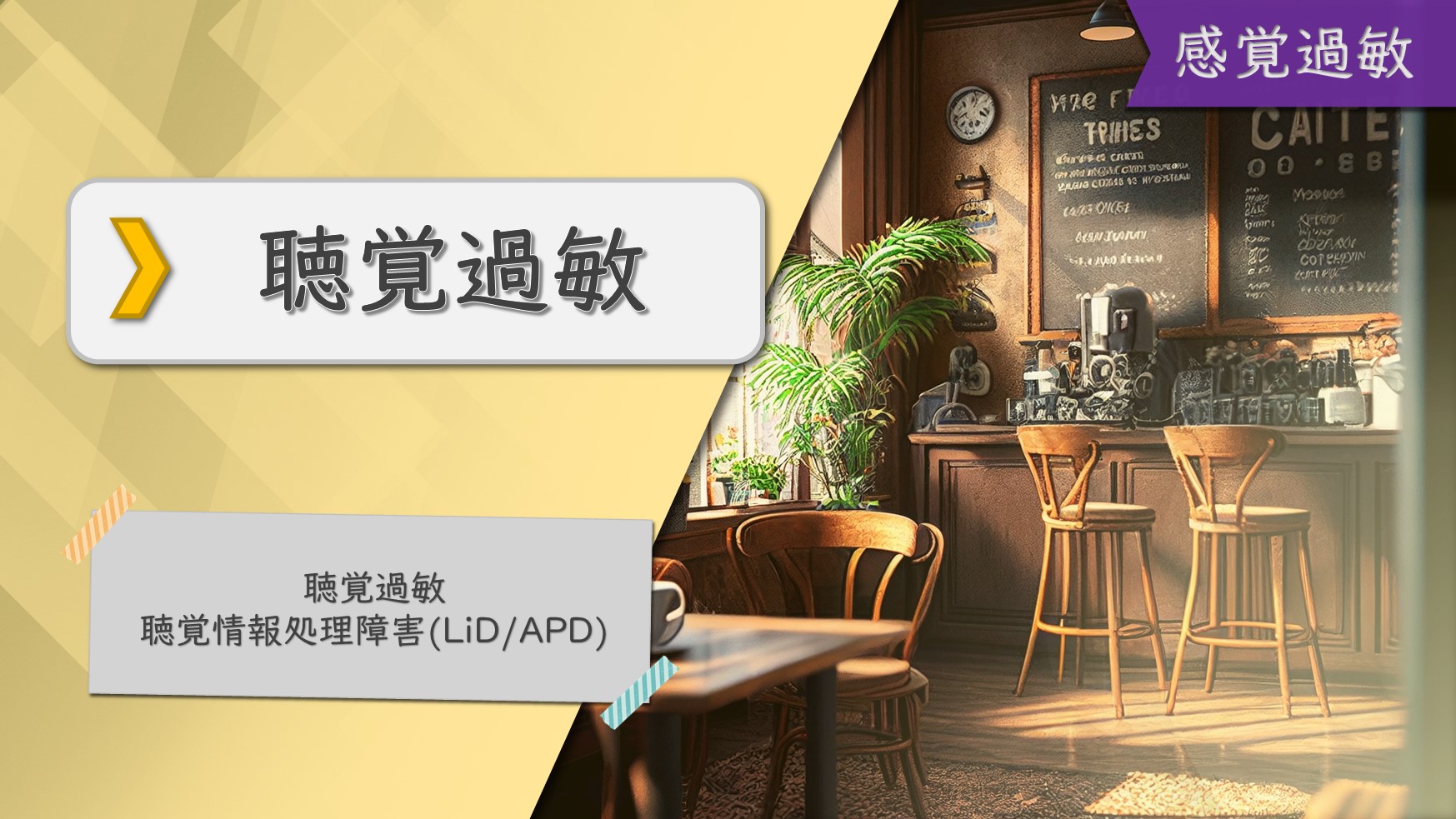
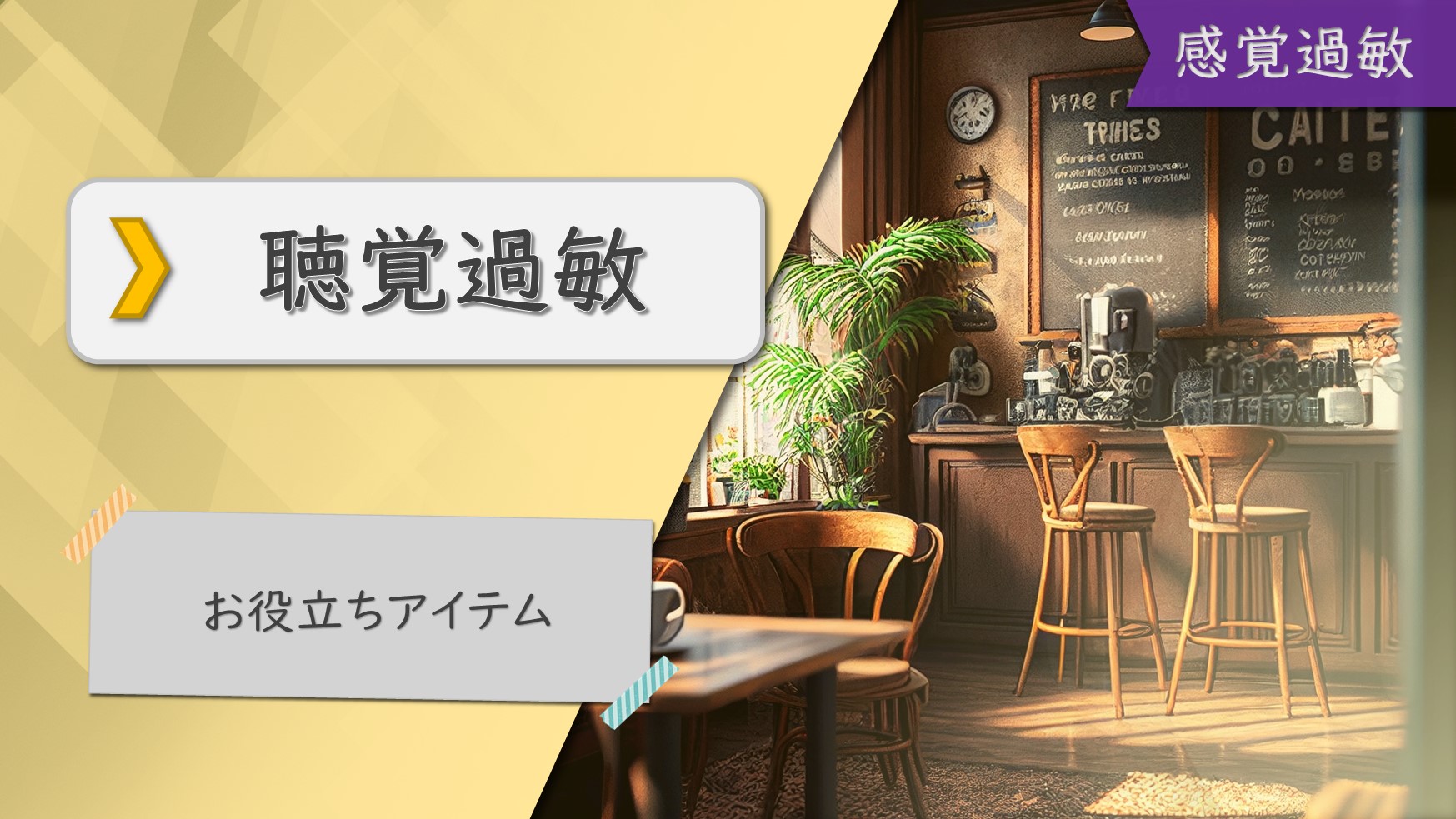

コメント