・誤学習の修正について知りたい人
・未学習の対応について知りたい人
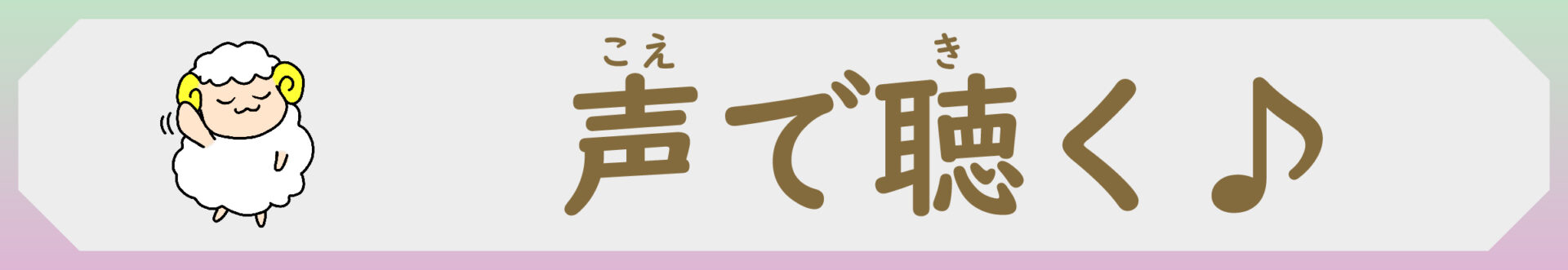
はじめに
今回は、誤学習についてその基礎知識と対処法まで、徹底的に見ていきたいと思います。
誤学習とは何か。未学習とは何か。見分け方は。誤学習の修正方法は。
すべて見ていきましょう。
れっつごー。

カテゴリはASDになってるけど、定型発達・発達障害関わらず、みんな誤学習する可能性があるよ!
誤学習と未学習
誤学習と混同しやすいものに、未学習があります。
未学習とは
「まだ方法を学べておらずどうしたらよいか分からない」状態。
不適切な行動へ繋がることもあります。
未学習の例
・ズボンの履き方が分からず、足を入れたり抜いたりして遊んでいる
・どうしたらおもちゃを買ってもらえるか分からずに泣く
誤学習とは
「過去にうまくいった不適切なパターンを繰り返すことで望んだ結果を得ようとする」状態。
学習しているパターン自体が不適切な行動である場合に問題となります。
誤学習の例
・ズボンで遊んでいれば履かせてくれると学習し、遊んでいる
・泣けばおもちゃを買ってもらえると学習し、泣いている
誤学習と未学習の見分け方
誤学習では、きっかけが発生してから行動に移るまでが早い傾向にあります。
誤学習では、過去に何回か同じ行動パターンを繰り返したり見たりして学習しています。
誤学習と未学習を見分けることは、実際には難しいです。
「未学習の可能性がある」と頭の片隅に置きながら、「正しい行動を伝えていく」という方法からアプローチするのが現実的であると感じます。
正しい行動を伝えたとしても、行動パターンが改善されない時は、誤学習の修正に入っていきます。
行動の分析の仕方
行動分析のステップ
誤学習を修正する時は、まず行動を分析します。
- Step1きっかけ
行動パターンの起点となる出来事です。
例:おもちゃ売り場の前を通る - Step2行動
誤学習の行動そのものです。
例:「買って!」と癇癪を起して泣く - Step3結果
行動の結果です。
例:おもちゃを買ってもらえる
誤学習では、Step1からStep3までの行動パターンを繰り返していることになります。
ステップごとの誤学習へのアプローチ
アプローチの詳細は後述します。
- STEP1きっかけに対するアプローチ
環境調整
確率操作
見通し - STEP2行動に対するアプローチ
分化強化
- STEP3結果に対するアプローチ
消去
未学習へのアプローチ
アプローチの方針としては「行動を伝えてできるようにする」です。
ここでは、「ズボンを上手に履く」という行動について、上手に伝える方法を書いていきます。
①目標行動を決める
具体的な目標を設定します。
この場合は「ズボンを履く」ですね。
②目標行動を分解する
「ズボンを履く」という行動は、細分化することができます。
①ズボンを広げる
②ズボンを持って座る
③ズボンに足を入れる
④立ち上がる
⑤おしりの上までズボンを上げる
もっと細分化もできますが、要は「行動のゴールを細かく設定する」ということが重要です。
逆上がりでも、鉄棒の持ち方や器具を使って足を上にあげる、といったステップを踏みますよね。
日常的なことに関して、もうすでにできる大人はステップをまとめてしまいがちです。
ステップを分けることは、「できた!」を大事にすることの他に、「ここまでならできる」という発達目安や「一個ずつできればいい」という大人側の心のゆとりにも繋がります。
③強化子を用意する
強化子とは、後述するABAの用語で「ゴールを達成できたご褒美」という意味です。
ゴールを達成できる=ご褒美がもらえる、というパターンの学習により、「この行動は正しい」と行動の強化を行うことができます。
強化子はモノである必要はなく、ハイタッチやハグなどのスキンシップ、一緒に遊ぶや「できたね!」という言葉がけでもOKです。
上記の細分化したステップをクリアできる度にあげられると良いですね。
この場合の強化子は「テストで100点取ったら100円あげる」というような強化子とは少し違うものであると私は思います。
テストの強化子が完全なるご褒美系なのに対し、ズボンの強化子は行動の後に「これで合っているよ」ということを伝えるものです。
予告があるかどうかは、強化子の役割に大きく影響すると感じます。
同時に、強化子は「不適切な行動も強化する」ことを忘れてはならず、強化子として選ぶものは不適切な行動の際に与えてはいけないことを肝に銘じておく必要があります。
④行動連鎖
行動連鎖とは、分解して学んだ行動を1つの行動に繋げていくことです。
行動連鎖には「順向連鎖」と「逆向連鎖」があります。
順向連鎖は最初から順に、「ズボンを広げる」から順に学びます。
逆向連鎖は最後から順に、「ズボンをおしりの上まであげる」から順に学びます。
決して最初から順に学ぶ必要はなく、お手伝いをして最後の最後だけ自分でやってみる(逆向連鎖)でも良いです。
学んだ行動を順番にこなすことで「ズボンを履く」という1つの行動に繋げることができます。
誤学習へのアプローチ
誤学習へのアプローチは、ABA(応用行動分析)を利用します。
ABAとは
ABAは、「行動の前後を分析することでその行動の目的を明らかにし、前後の環境を操作して問題行動を解消する分析方法」です。
特に乳幼児に対して適切な行動を伝える際に役に立ちます。
幼稚園年長・小学生あたりからは、本人の「こうしたい」という意思が強くなってくるので、ABAだけで療育を行うことは無理が出てきますが、療育の中心となる考え方であることは間違いありません。
きっかけに対するアプローチ
きっかけに対するアプローチは、まず最初に試すべきものです。
環境調整
環境を調整し、きっかけをなくしてしまうというアプローチです。
・部屋から飛び出してしまう
⇒ 鍵をかける
・爪かみをする
⇒ 手袋をする
・財布を持って行ってしまう
⇒ 財布を隠す
確率操作
きっかけを弱くするアプローチです。
・おもちゃを買って欲しくて泣く
⇒ おもちゃを売っている場所に行かない
・おなかが空いたら泣いてごはんを要求する
⇒ いつものご飯の前に軽食を用意しておく
見通し
見通しを与えることで、先手を打つアプロ―チです。
・お菓子を買って欲しくて泣く
⇒ 買い物前に「1個だけならOK」と約束事をする
行動に対するアプローチ
分化強化にはいくつか種類がありますが、今回は代替分化強化を利用します。
分化強化
不適切な行動の代わりに他の適切な行動を強化していくアプローチです。
「不適切な行動を止めさせる」ではなく「適切な行動に置き換える」アプローチであり、療育の基本ともいえるものです。
伝える系と褒める系があります。
【伝える系の例】
・構って欲しくて友達をたたく
⇒ 「構って欲しいんだよね」と気持ちを確認し、「肩をさわる」という行動を伝える
・大人に来て欲しいから泣く
⇒ 「さみしかったんだよね」と気持ちを確認し、「こっちきて!」と一緒に他の大人を呼ぶ
【褒める系の例】
・注目を浴びたくてスーパーで走り回る
⇒ 大人と一緒に歩いている時に褒める
・授業中に歩き回ってしまう
⇒ 座っている時に褒める
私は療育において「褒める」は最強だと思っています。
反抗期の子でさえ、褒められたい、認められたいと強く思っています。
適切な行動の時に褒める、は療育の基本であり、どんなアプローチも褒めるとセットで行うべきだと信じています。
結果に対するアプローチ
結果に対するアプローチは、きっかけ・行動に対するアプロ―チでは不十分な場合に行います。
本人にとってマイナスな行動であるため、必ず分化強化や「褒める」とセットで行います。
消去
不適切な行動に対して反応しないことで行動を消去していくアプローチです。
強化とは逆で、すでにある強化子を無くしていく方針になります。
人間の行動の意味は、4つあるとされます。
・要求
要求するための行動
・回避
嫌なことを避けるための行動
・注目獲得
注目を浴びるための行動
・感覚刺激
感覚刺激を得るための行動
感覚刺激は効果的な消去が難しいため、基本は分化強化で対応します。
要求に対する消去
要求には応じないというアプローチです。
・癇癪を起こしたらお菓子を買ってもらえる誤学習
⇒ 癇癪を起こしてもお菓子は買わない
回避に対する消去
決まっていることはやらせるというアプローチです。
・自傷行為をすれば勉強をしなくてもいい誤学習
⇒ 自傷行為をしても勉強はなくさない
※なぜ自傷行為を行うのか、勉強のレベルは適切か等、しっかり調査したうえでの対応であるべき
注目獲得に対する消去
注目しない、反応しないというアプローチです。
・いじわるをしたら注目してもらえるという誤学習
⇒ 本人への注目は行わない
リスクを伴うその他の方法
上記の方法でもどうにもならない時、リスクを負ってでもすぐに行動を止めさせる必要がある時は、これらの方法を使います。
本人にとっては「罰」となるため、必ず分化強化や「褒める」とセットで行います。
単独で行っても効果がないことは、見てもらえば分かると思います。
これらの方法はとても大きなリスクを伴い、一歩間違えれば虐待や二次障害に繋がる可能性すらあります。
それでも必要な場合があるため、ここに書き記すことを決めました。
別記事で書きますが、療育において「罰」はとても限定的な効果しか見込めません。
法的罰則が強化されても飲酒運転がなくならないことを見ても分かります。
これは学問・統計・私の経験すべてで答えが出ています。
やむなく「罰」を使わざるを得ない時は、必ず「期間を決めて」「褒めるとセットで」行ってください。
未だに罰で子どもたちをコントロールしようとしている支援者がいることを、とても残念に思います。
レスポンスコスト
好きなものを取り除くことで、不適切な行動を減らすアプローチです。
・構って欲しくて弟をたたく
⇒ お小遣いが減る
過剰修正
不適切な行動によって生じた状態を、範囲を拡大して修正させるアプローチです。
・注目してほしくてお茶をこぼす
⇒ こぼしたお茶とテーブル全部を拭いて掃除させる
タイムアウト
好きなものに触れる機会から一定時間離すアプローチです。
・友達と遊びたくて叩く
⇒ 一定時間別室に移動
誤学習を見る上で大切なこと
日常生活と誤学習
誤学習のきっかけは日常のいたるところに隠れています。
例えば、
・学校の先生が「ハイ!ハイ!」と声の大きい子を当てる傾向がある
・忙しい買い物の最中の癇癪に、ついお菓子を買ってしまった
・黄色信号で走って横断歩道を渡ってしまった
・おもちゃを買って欲しくて癇癪を起こしたら、通りがかりの人が「なんで買ってあげないの」と保護者を責めた
しかし、人間は完璧には生きられません。
誤学習に気を取られすぎてもっと大事なことを見逃してしまっては本末転倒です。
大人はありのままの姿を見せ、誤学習の修正には専門家の手を借り、それが誤った行動であることを「あの時はこういう理由で、間違ったことをしちゃったんだ、それはこういう意味で間違っているんだ」としっかりと伝えることこそが大事だと思います。
キラキラした理想ではなく、ドロドロしていても現実的な支援を行っていきたいですね。
誤学習と発達障害
誤学習は全ての人に当てはまるため、あえて最後に書きます。
誤学習は発達障害と大きく関係があります。
ASDであれば、同一性保持やパターン学習、ハイコントラスト特性から、誤学習が定着しやすく修正が難しい傾向にあります。
ADHDであれば、衝動性や多動性から、誤学習が派手になる、誤学習だと誤認されやすい傾向にあります。
全ての行動には理由があります。
その理由が大切であって、アプローチすべきなのも理由です。
決して不適切な行動だけを見ないよう、常に心掛けたいですね。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
誤学習は時間をかけての修正が必要になってきます。
是非専門家と一緒にゆっくりと修正をし、本人が生きやすいようにしてあげたいですね。
それではまたお逢いしましょう。
【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】
発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。
通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。
「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」
三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。
現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。
是非お困りごとをお聞かせください。
※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。


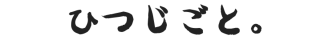
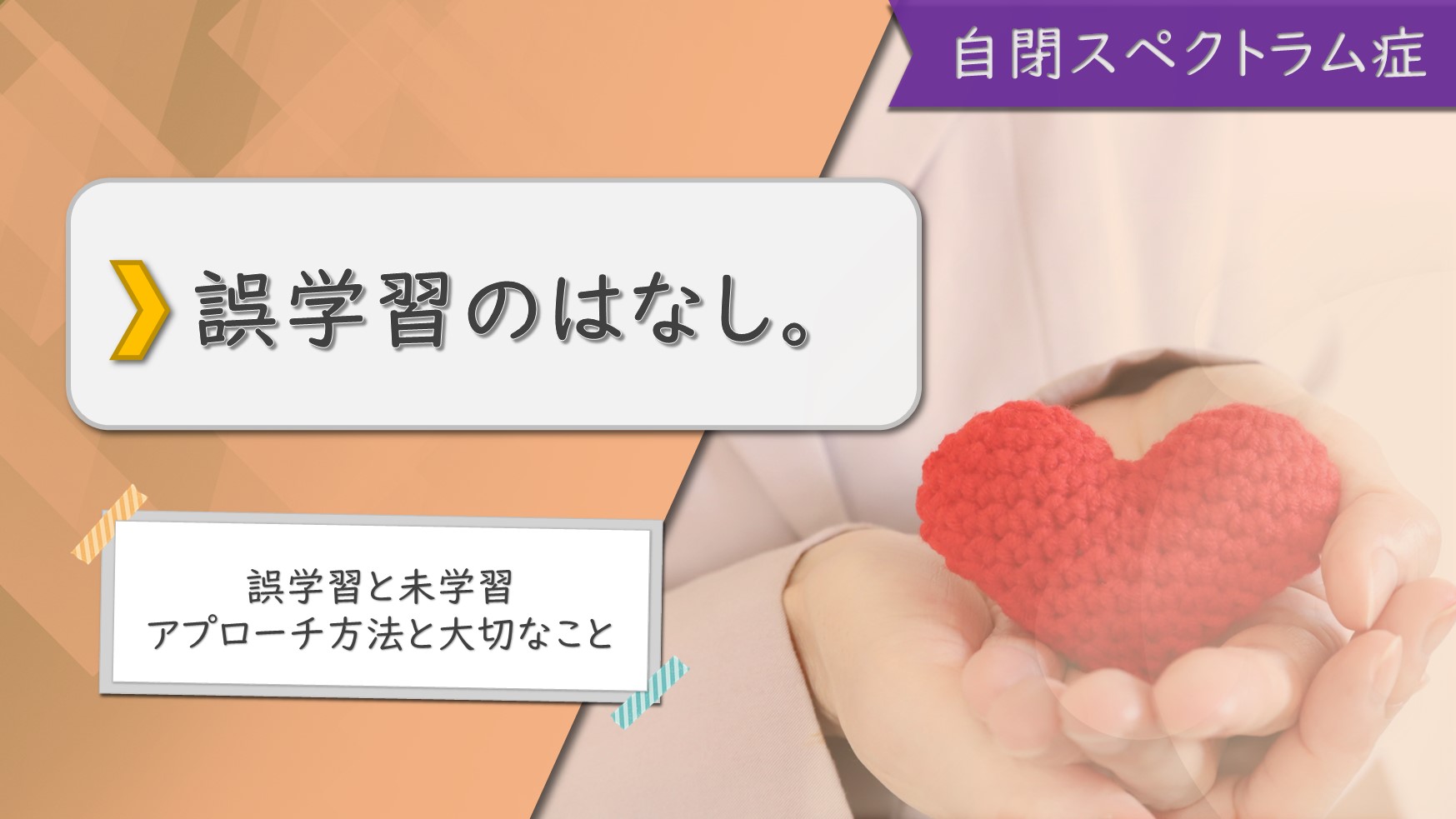
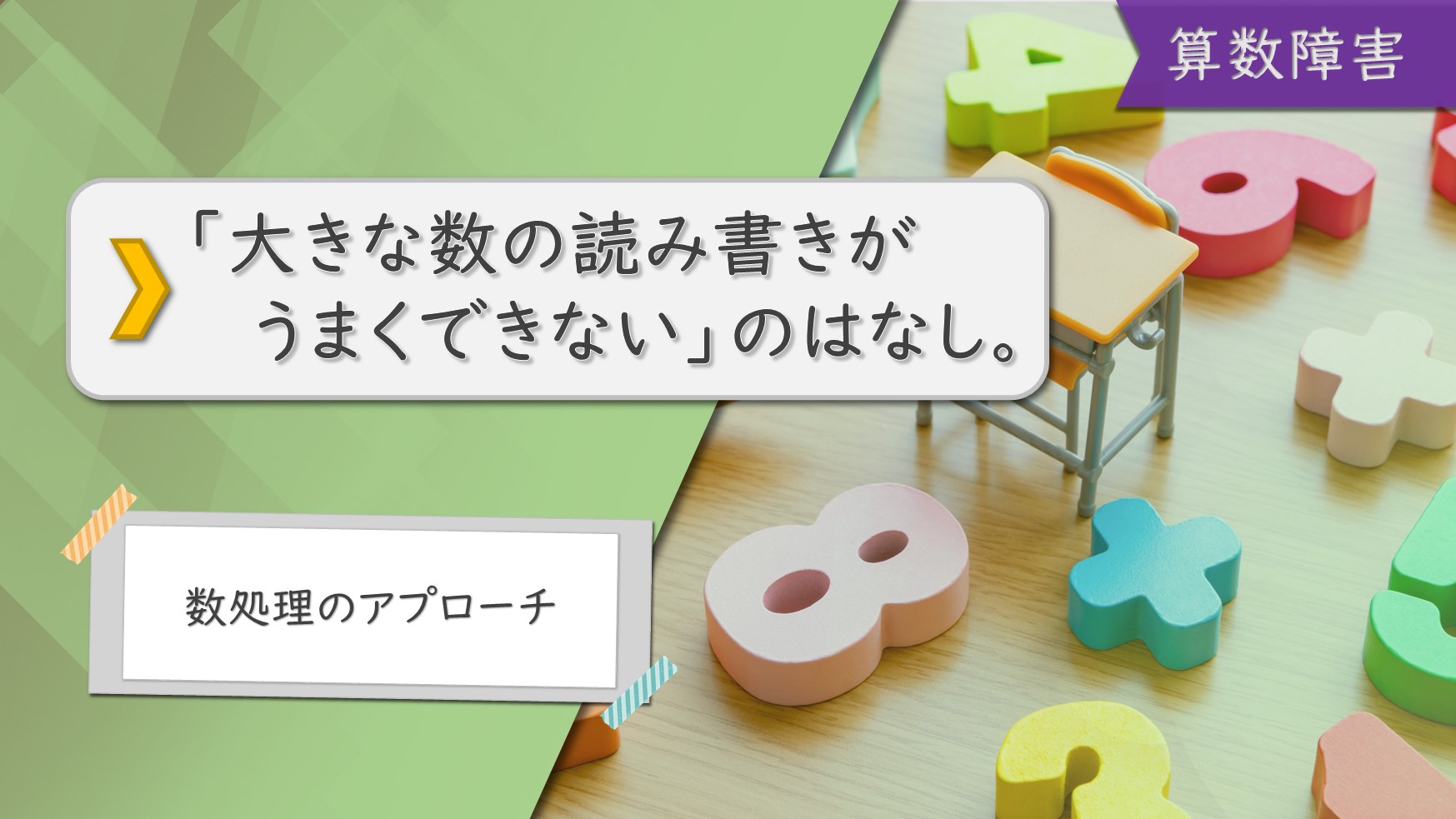
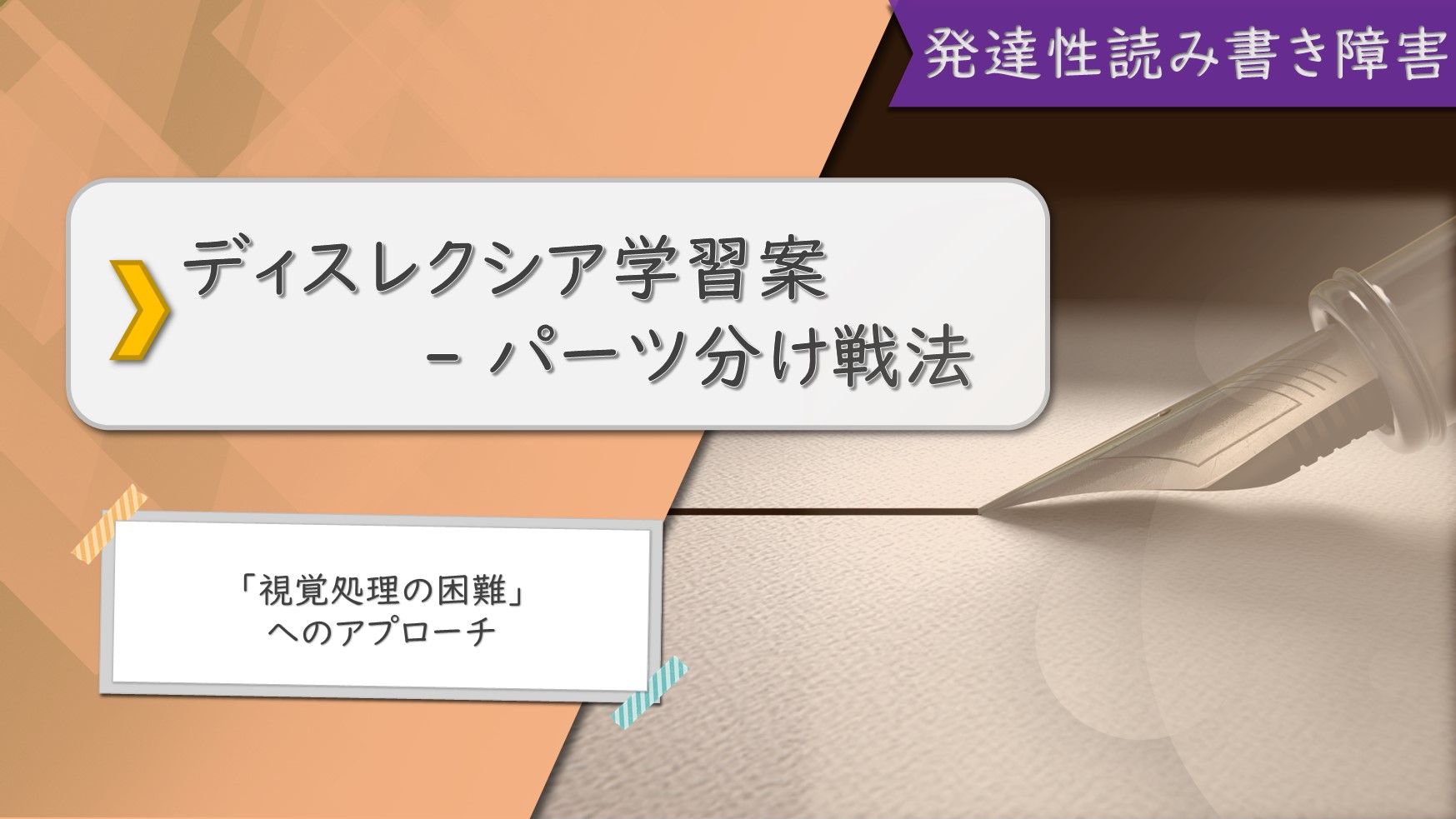

コメント