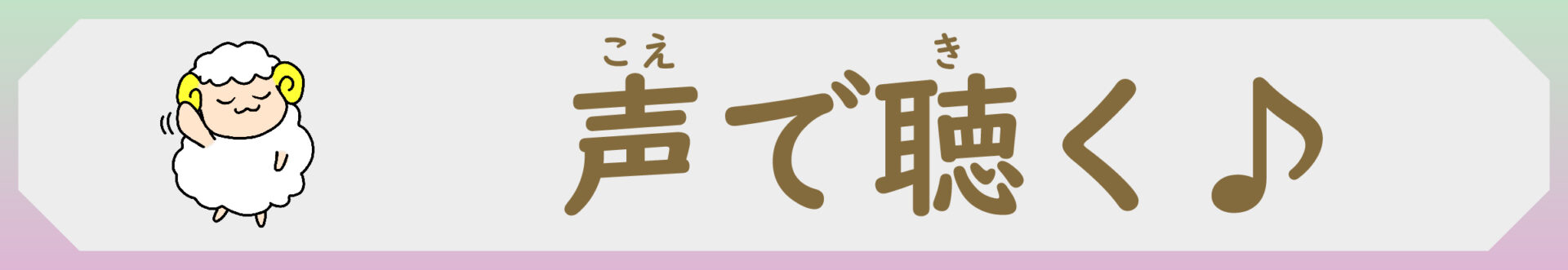
どうも、結婚指輪が外れなくなってしょぼんとしているひつじぃです。
今回は、「学習支援」というものについて、綴っていこうかと思います。
そもそも学習支援ってなに?

まぁ明確な定義はないけど!
私が思う「学習支援」とは、
『学習がうまくいかなくて困っている人に、専門知識や経験を下に「どうやったら楽しく楽に学習ができるか」一緒に考える』
ことです。
ここで、一つ疑問が湧いてくる人がいると思います。
「え、別に勉強できなくても良くない?」
はい、そうです。基本は私もそう思います。
「じゃぁ学習支援なんて必要なくない?」
それは違う!!!
学習支援は必要なんです。
まず前提からお話しします。
「勉強」と「学習」は、ちょっと違うんです。
学習はもう少し広い範囲、例えば「新しいスマホ買ったけど使い方慣れなきゃ…」ということも含むんですね。
そのことを踏まえ、学習支援が何故必要かを一緒に考えてみましょう。
学習支援の必要性と目的
結論から。目的は大きく分けて二つです。
さて、難しい言葉が出てきました。一つ一つ見ていきましょう。
①学校の勉強が上手くいかないことによる二次障害の防止と自己肯定感の向上
日本では、小学校入学から中学校卒業まで、必ず学校に所属します。
学校は、家庭と同じくらいの時間を過ごし、同じくらい大切な「居場所」になることが多いです。
その学校は「勉強ができるかどうか」を大きな基準として生徒たちを評価します。
そして、家庭もその評価に引っ張られがちになります。
テストの点数、通知表、授業参観…。
家庭でも少しは気にしますよね。
そこで一つの問題が生まれます。
見ているだけで苦しくなりそうな言葉が並びます。
するとどうなるか。
自尊心(自分は価値のある人間だという思い)の不必要な低下が起こります。
当たり前ですね。頑張りを評価してもらえず苦しみや困り感を見てもらえないのですから。
自尊心の低下は、コミュニケーションを始めとする日常生活にも影響を及ぼし、果ては生き方自体にも関わります。
自分の価値を低く見すぎてしまうからです。
そんな時助けを求める先は、もう一つの居場所である家庭ですが、そちらも学校の評価にどうしても引っ張られてしまうため、中々難しい。
ここで、その困り感を解消するために「学習支援」が自然と必要になってくるのです。
なぜ勉強が上手くいかないか、その可能性と理由については、以下の記事等へお進みください。
では、二つ目にいきましょう。

疲れていませんか?疲れた方は迷いなく休んでくださいね。記事は逃げませんから、大丈夫!
②社会の技術の進歩に適応し社会で生き続ける力を育む

質問だよ!
この10年で、社会に広まった新しい「モノ」は何が思いつきますか?
スマホ、スマートホーム、電子決済、タブレット、セルフレジの機械…。
全体的に機械系になってしまいましたが、沢山ありますね。
そして、これらを使えないと日常生活に支障が出るレベルで、社会に広まっていますね。
さらに10年後、車は自動運転となり、キーボードは消え全てタッチ式、お家の鍵もなくなるかも。
そうした時、新しい形の「モノ」に適応できなければ、日常生活すら危うくなるのです。
私たちは、知らず知らずのうちに「学習」と「適応」を繰り返しているんですね。
しかしこの学習が難しい場合、それは新しい「モノ」に適応できない、ということを意味します。
そしてこれは、学校の勉強とも繋がりがあります。
説明書を読み理解する力、完成図から想像して組み立てる力、ボタンの配置を見て機能を想像する力、それがどんな「モノ」なのか情報を集める力。
難しいことは助けを求めれば良いのですが、日常的に助けを求め続けることは難しく、自分でできるに越したことはありません。
その困り感を予防するために、「学習支援」が自然と必要になってくるのです。
学習支援のゴール
学習支援の具体的なゴールは人それぞれです。
ですが、大筋は同じです。
「自立し自分らしく生きる力を育む」
どの支援も、大体ここに収束します。
登れば消えるハシゴ、という表現があります。
「支援が終了すれば、気にならなくなること」です。
自尊心の回復もそうですが、学習支援もこれに当てはまると私は思います。
「自分なりの学び方」「自分でできること、助けを求めるべきことの理解」
これらは、一度身についたら生涯忘れません。
「支援にベストは存在しない」と、私は考えています。
沢山あるベターからあーでもないこーでもないと知識と経験をフル動員させ、当人と一緒に考える支援こそが、支援というものの本来の在り方だと、私は思います。
私も一生をかけて、書籍や大人や子どもたちから学び続けます。
今まさにお困りの方、保護者の方、支援者の方、教育関係者の方、支援に興味を持たれる方。
ここから、私と一緒に学びませんか。
学習支援の世界へ、ようこそ。

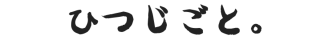
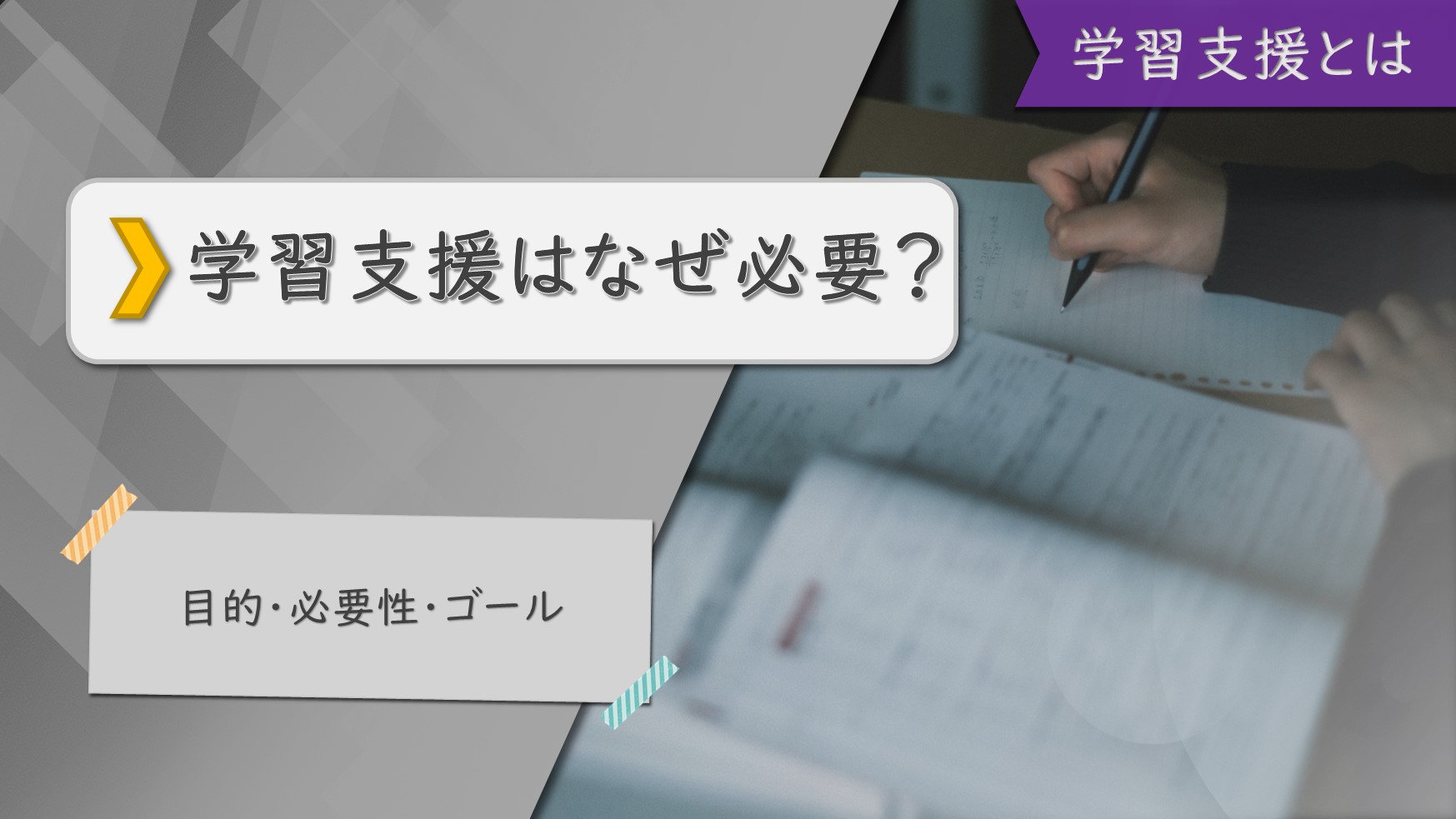
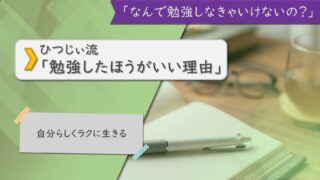
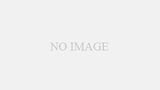
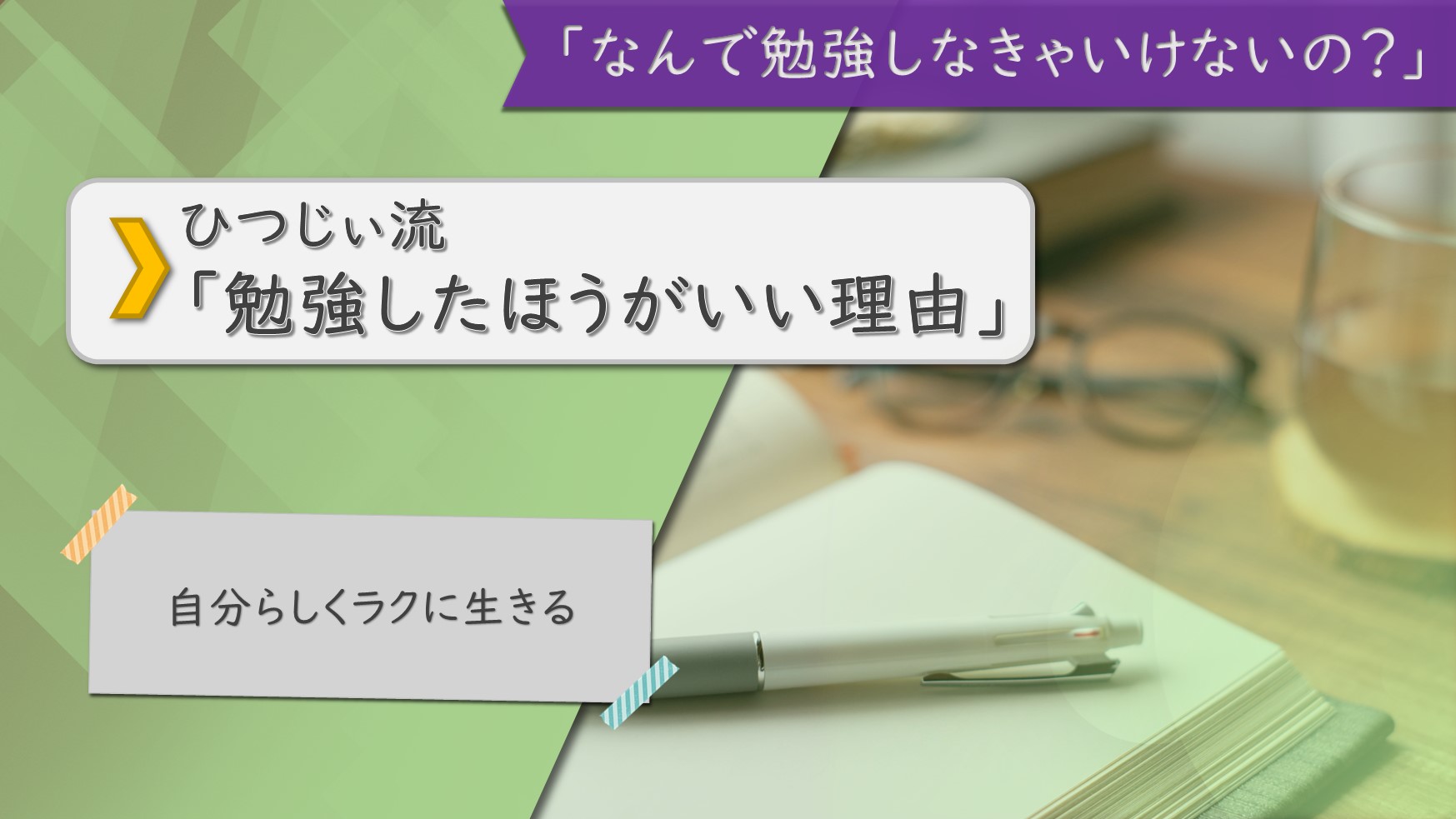
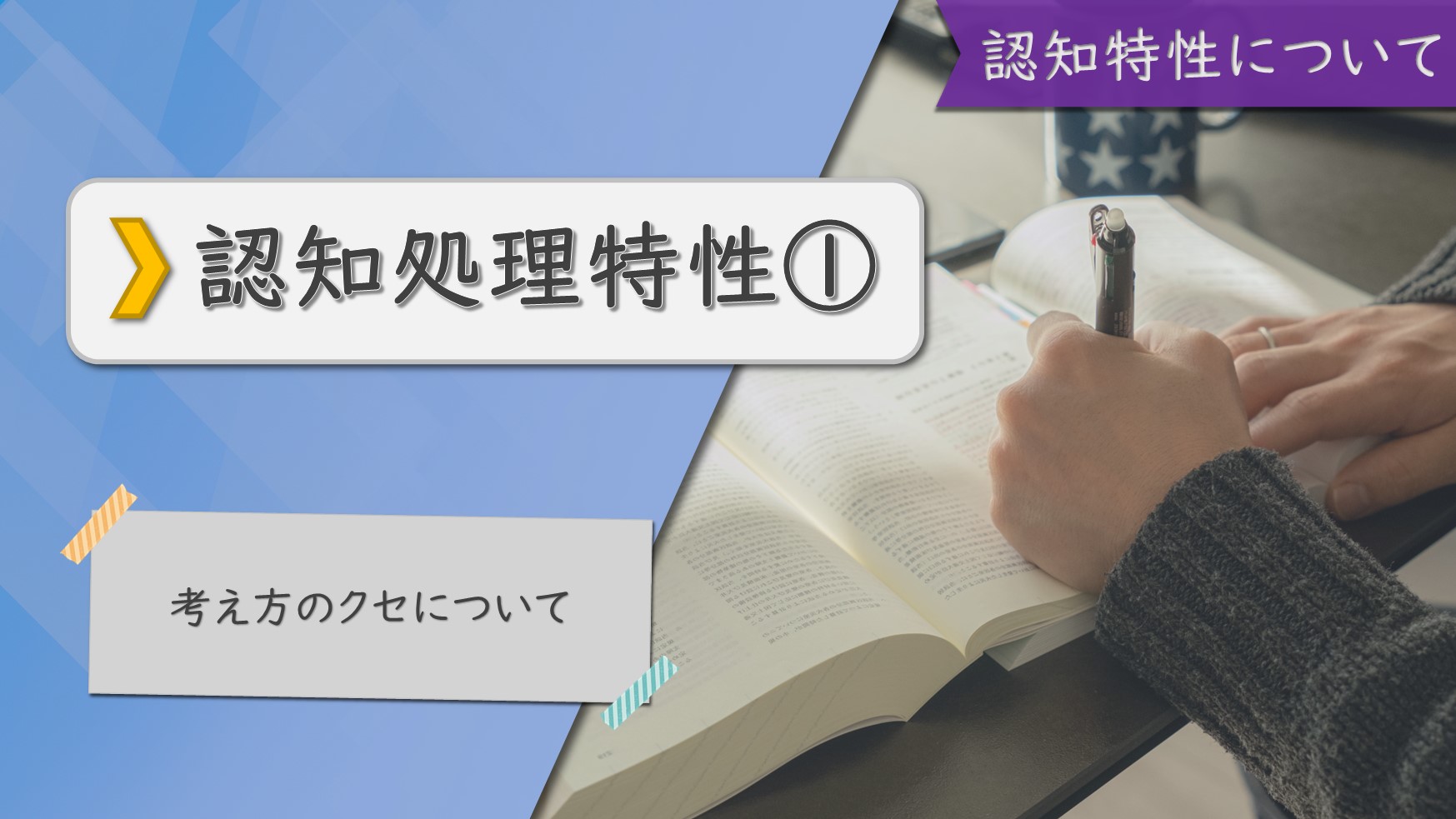

コメント